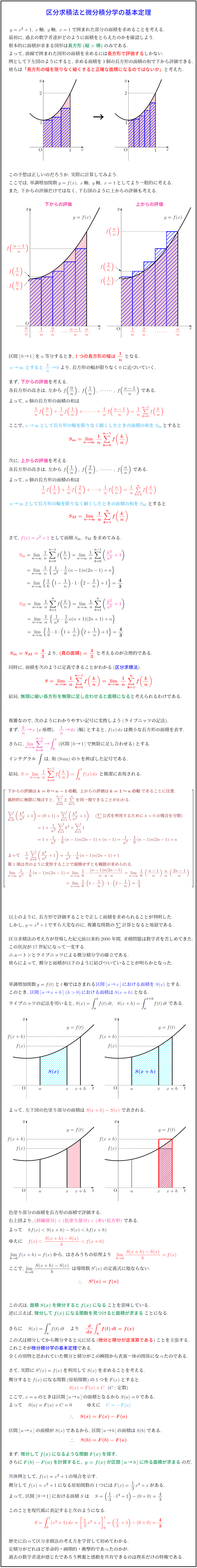
y=x²+1,\ x軸,\ y軸,\ x=1$で囲まれた部分の面積を求めることを考える. 最初に,\ 過去の数学者達がどのように面積をとらえたのかを確認しよう. 根本的に面積が求まる図形は\長方形(縦$$横)のみである. よって,\ 曲線で囲まれた図形の面積を求めるには長方形で評価するしかない. 例として下左図のようにすると,\ 求める面積を3個の長方形の面積の和で下から評価できる. 彼らは「長方形の幅を限りなく細くすると正確な面積になるのではないか」と考えた. この予想は正しいのだろうか.\ 実際に計算してみよう. ここでは,\ 単調増加関数$y=f(x),\ x軸,\ y軸,\ x=1$としてより一般的に考える. また,\ 下からの評価だけではなく,\ 下右図のように上からの評価も考える. 区間$[0→1]$を$n$等分するとき,\ ${1つの長方形の幅は\ 1n$となる. $n→∞\ とすると\ 1n→0}$より,\ 長方形の幅が限りなく0に近づいていく. まず,\ 下からの評価を考える. よって,\ $n$個の長方形の面積の和は ここで,\ $n→∞$として長方形の幅を限りなく細くしたときの面積の和を$S_m$}とすると\ 次に,\ 上からの評価を考える. 各長方形の高さは よって,\ $n$個の長方形の面積の和は $n→∞$として長方形の幅を限りなく細くしたときの面積の和を$S_M$}とすると さて,\ $f(x)=x²+1}$として面積$S_m,\ S_M$を求めてみる. (真の面積)=43$\ と考えるのが合理的である. 同時に,\ 面積を次のように定義できることがわかる(区分求積法 結局,\ 無限に細い長方形を無限に足し合わせると面積になると考えられるわけである. 複雑なので,\ 次のようにわかりやすい記号に変換しよう(ライプニッツの記法). まず,\ $ kn→x}\ (x座標),1n→dx}\ (幅)$とすると,\ $f(x)dx$は微小な長方形の面積を表す(区間$[0→1]$で無限に足し合わせる)とする. インテグラル$∫$は,\ $和(Sum})のS}を伸ばした記号である.$f(x)dx}$\ と簡潔に表現される. 下からの評価は{k=0~n-1の和},\ 上からの評価は{k=1~nの和}であることに注意. 最終的に無限に飛ばすと,\ Σk=0}{n-1}とΣを同一視できることがわかる. 公式を利用するためにk=0の場合を分割) 第1項は次のように変形することで展開せずとも極限が求められる. 以上のように,\ 長方形で評価することで正しく面積を求められることが判明した. ただし,\ $y=x²+1$ですら大変なのに,\ 複雑な関数の$Σ}$計算となると地獄である. 区分求積法の考え方が登場した紀元前以来約2000年間,\ 求積問題は数学者を苦しめてきた. この状況が17世紀になって一変する.\ ニュートンとライプニッツによる微分の発明である. さらに,\ 彼らは以下のようにして微分と面積が結びつくことを発見した. 単調増加関数$y=f(t)とt軸ではさまれる区間[a→x]における面積をS(x)}とする.$ このとき,\ $区間[a→x+h]\ (h0)における面積はS(x+h)}$となる. ライプニッツの記法を用いると,\ $S(x)=∫a}{x}f(t)dt,S(x+h)=∫a}{x+h}f(t)dt$\ である. よって,\ 左下図の色塗り部分の面積は\ $S(x+h)-S(x)}$\ で表される. 色塗り部分の面積を長方形の面積で評価する. 右上図より,\ $(斜線部分)(色塗り部分)(赤い長方形)}$\ である. よって $hf(x)S(x+h)-S(x)hf(x+h)$ ゆえに $f(x){S(x+h)-S(x)}{h}f(x+h)}$ $lim[h→0]f(x+h)=f(x)から,\ はさみうちの原理より lim[h→0]{S(x+h)-S(x)}{h}=f(x)}$ ここで,\ $lim[h→0]{S(x+h)-S(x)}{h}\ は導関数S'(x)の定義式に他ならない.$ 面積S(x)を微分するとf(x)になる$ことを意味している.微分してf(x)になる関数を見つけると面積が求まる$ことになる. さらに $S(x)=∫a}{x}f(t)dt よ∫a}{x}f(t)dt=f(x)$ この式は積分してから微分すると元に戻る(微分と積分が逆演算である)ことを主張する. これこそが微分積分学の基本定理である. 全くの別物と思われていた微分と積分がこの瞬間から表裏一体の関係になったのである. さて,\ 実際に$S'(x)=f(x)$を利用して$S(x)$を求めることを考える. 微分すると$f(x)$になる関数(原始関数)の1つを$F(x)$とすると S(x)=F(x)+C}(C:定数)$} ここで,\ $x=aのときは区間[a→a]の面積となるからS(a)=0である.$ よって $S(a)=F(a)+C=0 ゆえに C=-F(a)}$ S(x)=F(x)-F(a)$} 区間$[a→x]$の面積が$S(x)$であるから,\ 区間$[a→b]$の面積は$S(b)$である. {S(b)=F(b)-F(a)$} 微分してf(x)になるような関数F(x)を探す.$ F(b)-F(a)を計算すると,\ y=f(x)が区間[a→b]に作る面積が求まるのだ.$ 具体例として,\ $f(x)=x²+1$の場合を示す. 微分して$f(x)=x²+1$になる原始関数の1つには$F(x)=13x³+x$がある. よって,\ 区間$[0→1]$における面積$S$は このことを現代風に表記すると次のようになる. 歴史に沿って区分求積法の考え方を学習して初めてわかる. 定積分がどれほど革命的・画期的・衝撃的であったのかが. 過去の数学者達が感じたであろう興奮と感動を共有できるのは理系だけの特権である

