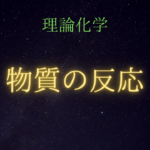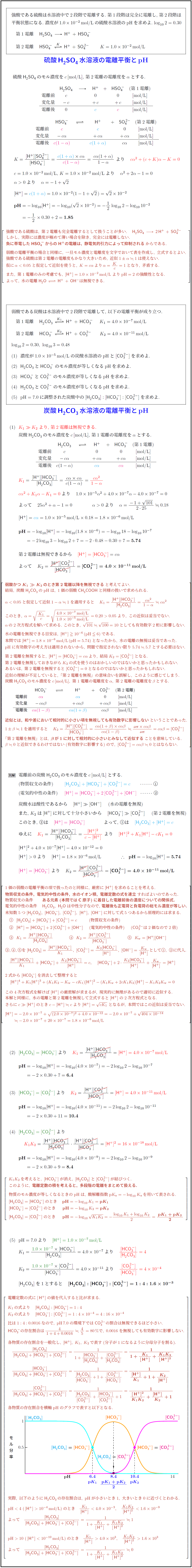
強酸である硫酸は水溶液中で2段階で電離する. 第1段階は完全に電離し, 第2段階は平衡状態になる. 濃度が1.0×10⁻² mol/Lの硫酸水溶液のpHを求めよ. log₁₀2=0.30
第1電離 H₂SO₄ → H⁺ + HSO₄⁻
第2電離 HSO₄⁻ ⇄ H⁺ + SO₄²⁻ K=1.0×10⁻² mol/L
硫酸 H₂SO₄ のモル濃度を c [mol/L], 第2電離の電離度を α とする.
H₂SO₄ → H⁺ + HSO₄⁻ (第1電離)
電離前 c 0 0
変化量 −c +c +c
電離後 0 c c
HSO₄⁻ ⇄ H⁺ + SO₄²⁻ (第2電離)
電離前 c c 0
変化量 −cα +cα +cα
電離後 c(1−α) c(1+α) cα
K = [H⁺][SO₄²⁻]/[HSO₄⁻] = c(1+α)×cα / c(1−α) = cα(1+α)/(1−α)
より cα² + (c+K)α − K = 0
c=1.0×10⁻² mol/L, K=1.0×10⁻² mol/L より
α² + 2α − 1 = 0
α > 0 より α = −1 + √2
[H⁺] = c(1+α) = 1.0×10⁻² (1−1+√2) = √2 × 10⁻²
pH = −log₁₀[H⁺] = −log₁₀(√2×10⁻²) = −(1/2)log₁₀2 − log₁₀10⁻²
= −0.5×0.30 + 2 = 1.85
強酸である硫酸は, 第2電離も完全電離するとして扱うことが多い.
H₂SO₄ → 2H⁺ + SO₄²⁻
しかし, 実際には濃度が極めて薄い場合を除き, 完全には電離しない.
負に帯電した HSO₄⁻ からの H⁺ の電離は, 静電的引力によって抑制されるからである.
弱酸の電離平衡の場合と同様に, 一旦モル濃度と電離度を文字でおいて表を作成し, 立式するとよい.
強酸である硫酸は第2電離の電離度もかなり大きいため, 近似 1±α ≈1 は使えない.
仮に α < 0.05 と仮定して近似を使うと, K=cα より α=K/c=1 となり, 矛盾する.
また, 第1電離のみの考慮でも [H⁺]=1.0×10⁻² mol/L より pH=2 の強酸性となる.
よって, 水の電離 H₂O ⇄ H⁺ + OH⁻ は無視できる.
弱酸である炭酸は水溶液中で2段階で電離して, 以下の電離平衡が成り立つ.
第1電離 H₂CO₃ ⇄ H⁺ + HCO₃⁻ K₁=4.0×10⁻⁷ mol/L
第2電離 HCO₃⁻ ⇄ H⁺ + CO₃²⁻ K₂=4.0×10⁻¹¹ mol/L
log₁₀2=0.30, log₁₀3=0.48
(1) 濃度が1.0×10⁻⁵ mol/Lの炭酸水溶液のpHと[CO₃²⁻]を求めよ.
(2) H₂CO₃とHCO₃⁻のモル濃度が等しくなるpHを求めよ.
(3) HCO₃⁻とCO₃²⁻のモル濃度が等しくなるpHを求めよ.
(4) H₂CO₃とCO₃²⁻のモル濃度が等しくなるpHを求めよ.
(5) pH=7.0に調整された炭酸中の[H₂CO₃]:[HCO₃⁻]:[CO₃²⁻]を求めよ.
(1) K₁≫K₂より, 第2電離は無視できる.
炭酸 H₂CO₃ のモル濃度を c [mol/L], 第1電離の電離度を α とする.
H₂CO₃ ⇄ H⁺ + HCO₃⁻ (第1電離)
電離前 c 0 0
変化量 −cα +cα +cα
電離後 c(1−α) cα cα
K₁ = [H⁺][HCO₃⁻]/[H₂CO₃] = cα×cα / c(1−α) = cα²/(1−α)
cα² + K₁α − K₁ = 0
1.0×10⁻⁵α² + 4.0×10⁻⁷α − 4.0×10⁻⁷ = 0
よって 25α² + α − 1 = 0
α>0 より α = (−1 + √101)/(2×25) ≈ 0.18
[H⁺] = cα = 1.0×10⁻⁵ × 0.18 = 1.8×10⁻⁶ mol/L
pH = −log₁₀[H⁺] = −log₁₀(1.8×10⁻⁶) = −log₁₀18 − log₁₀10⁻⁷
= −2log₁₀3 − log₁₀2 + 7 = −2×0.48 − 0.30 + 7 = 5.74
第2電離は無視できるから [H⁺]=[HCO₃⁻]=cα
よって K₂ = [H⁺][CO₃²⁻]/[HCO₃⁻] = [CO₃²⁻] = 4.0×10⁻¹¹ mol/L
弱酸かつ K₁≫K₂ のとき第2電離以降を無視できると考えてよい.
結局, 炭酸 H₂CO₃ の pH は, 1価の弱酸 CH₃COOH と同様の扱いで求められる.
α<0.05 と仮定して近似 1−α≈1 を適用すると
K₁ = [H⁺][HCO₃⁻]/[H₂CO₃] = cα²/(1−α) ≈ cα²
このとき α = √(K₁/c) = √(4.0×10⁻⁷ / 1.0×10⁻⁵) = 0.20 > 0.05 より, この近似は妥当でない.
α の2次方程式を解いて求める. このとき √101 ≈ √100 = 10 としても有効数字2桁に影響しない.
水の電離を無視できる目安は [H⁺]≥10⁻⁶ (pH≤6) である.
本問では [H⁺]=1.8×10⁻⁶ mol/L (pH=5.74) となったから, 水の電離の無視は妥当であった.
pHに有効数字の考え方は適用されないから, 問題で指定されない限り5.74≈5.7とする必要はない.
第2電離を無視すると, [H⁺]=[HCO₃⁻]=cα より, 結局 K₂=[CO₃²⁻] となる.
第2電離を無視しておきながら K₂ の式を使うのはおかしいのではないかと思ったかもしれない.
あるいは, 第2電離を無視すると [CO₃²⁻]=0 となるのではないかと思ったかもしれない.
近似の理解が不足していると, 「第2電離を無視」の意味合いを誤解し, このように感じてしまう.
炭酸 H₂CO₃ のモル濃度を c [mol/L], 第1電離の電離度を α, 第2電離の電離度を β とする.
HCO₃⁻ ⇄ H⁺ + CO₃²⁻ (第2電離)
電離前 cα cα 0
変化量 −cαβ +cαβ +cαβ
電離後 cα(1−β) cα(1+β) cαβ
近似とは, 和や差において相対的に小さい項を無視しても有効数字に影響しないということであった.
1±β≈1 を適用すると
K₂ = [H⁺][CO₃²⁻]/[HCO₃⁻] = cα(1+β)×cαβ / cα(1−β) ≈ cαβ = [CO₃²⁻]
「第2電離を無視」とは, β が 1 に対して相対的に小さいとみなして近似することを意味している.
β≈0 と近似できるわけではない (有効数字に影響する) ので, [CO₃²⁻]=cαβ≈0 とはならない.
(2) [H₂CO₃]=[HCO₃⁻] より K₁=[H⁺][HCO₃⁻]/[H₂CO₃]=[H⁺]=4.0×10⁻⁷ mol/L
pH = −log₁₀[H⁺] = −log₁₀(4.0×10⁻⁷) = −2log₁₀2 − log₁₀10⁻⁷
= −2×0.30 + 7 = 6.4
(3) [HCO₃⁻]=[CO₃²⁻] より K₂=[H⁺][CO₃²⁻]/[HCO₃⁻]=[H⁺]=4.0×10⁻¹¹ mol/L
pH = −log₁₀[H⁺] = −log₁₀(4.0×10⁻¹¹) = −2log₁₀2 − log₁₀10⁻¹¹
= −2×0.30 + 11 = 10.4
(4) [H₂CO₃]=[CO₃²⁻] より
K₁K₂=[H⁺][HCO₃⁻]/[H₂CO₃] × [H⁺][CO₃²⁻]/[HCO₃⁻] = [H⁺]² = 16×10⁻¹⁸ mol/L
pH = −log₁₀[H⁺] = −log₁₀(4.0×10⁻⁹) = −2log₁₀2 − log₁₀10⁻⁹
= −2×0.30 + 9 = 8.4
K₁K₂を考えると, [HCO₃⁻]が消え, [H₂CO₃]と[CO₃²⁻]が結びつく.
このように, 電離定数の積を考えると, 多段階の電離をまとめて扱える.
物質のモル濃度が等しくなるときのpHは, 酸解離指数 pKₐ=−log₁₀Kₐ を用いて表される.
[H₂CO₃]=[HCO₃⁻]のとき pH=pK₁
[HCO₃⁻]=[CO₃²⁻]のとき pH=pK₂
[H₂CO₃]=[CO₃²⁻]のとき pH=−log₁₀√(K₁K₂)=−(log₁₀K₁+log₁₀K₂)/2=(pK₁+pK₂)/2
(5) pH=7.0より [H⁺]=1.0×10⁻⁷ mol/L
K₁=[H⁺][HCO₃⁻]/[H₂CO₃]=4.0×10⁻⁷ より [HCO₃⁻]/[H₂CO₃]=4
K₂=[H⁺][CO₃²⁻]/[HCO₃⁻]=4.0×10⁻¹¹ より [CO₃²⁻]/[HCO₃⁻]=4×10⁻⁴
[H₂CO₃]を1とすると [H₂CO₃]:[HCO₃⁻]:[CO₃²⁻]=1:4:1.6×10⁻³
電離定数の式に[H⁺]の値を代入すると比が求まる.
K₁の式より [H₂CO₃]:[HCO₃⁻]=1:4
K₂の式より [HCO₃⁻]:[CO₃²⁻]=1:4×10⁻⁴=4:16×10⁻⁴
比は1:4:0.0016なので, pH7.0の環境下ではCO₃²⁻の割合は無視できるほど小さい.
HCO₃⁻の存在割合は 4/(1+4+0.0016) ≈ 4/5 = 80% で, 0.0016を無視しても有効数字に影響しない.
各物質の存在割合を一般化し, [H⁺], K₁, K₂ で表す(分子が1になるように分母分子を割る).
[H₂CO₃]/([H₂CO₃]+[HCO₃⁻]+[CO₃²⁻]) = 1 / (1 + K₁/[H⁺] + K₁K₂/[H⁺]²)
[HCO₃⁻]/([H₂CO₃]+[HCO₃⁻]+[CO₃²⁻]) = 1 / ([H⁺]/K₁ + 1 + K₂/[H⁺])
[CO₃²⁻]/([H₂CO₃]+[HCO₃⁻]+[CO₃²⁻]) = 1 / ([H⁺]²/(K₁K₂) + [H⁺]/K₂ + 1)
各物質の存在割合を横軸pHのグラフで表すと以下となる.
実際, 以下のように H₂CO₃ の存在割合は, pHが小さいとき1, 大きいとき0に近づくとわかる.
pH<4 ([H⁺]>10⁻⁴ mol/L) のとき K₁/[H⁺]<4.0×10⁻³, K₁K₂/[H⁺]²<1.6×10⁻⁹
よって [H₂CO₃]/([H₂CO₃]+[HCO₃⁻]+[CO₃²⁻]) = 1/(1 + K₁/[H⁺] + K₁K₂/[H⁺]²) ≈ 1
pH>10 ([H⁺]<10⁻¹⁰ mol/L) のとき K₁/[H⁺]>4.0×10³, K₁K₂/[H⁺]²>1.6×10³
よって [H₂CO₃]/([H₂CO₃]+[HCO₃⁻]+[CO₃²⁻]) = 1/(1 + K₁/[H⁺] + K₁K₂/[H⁺]²) ≈ 0