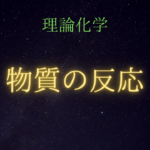英語名は「Le Chatelier’s principle」なので「ル・シャトリエの原理」である。ル・シャトリエはフランスの化学者。
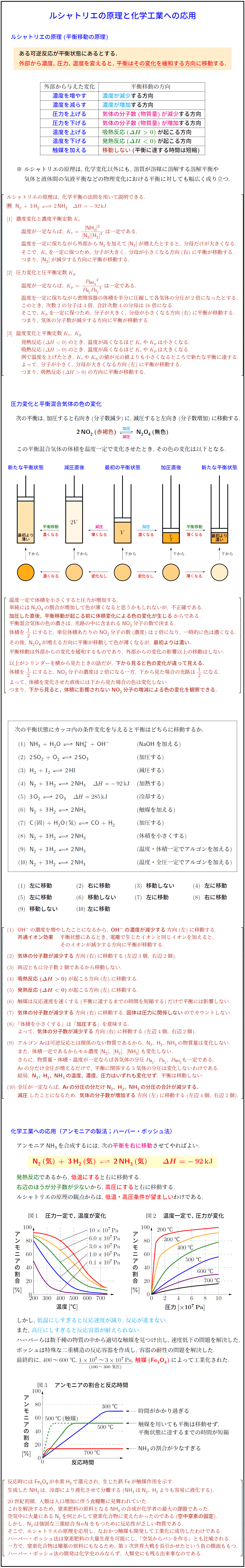
ルシャトリエの原理
外からの条件の変化(濃度, 温度, 圧力など)に対して, 系がその影響を打ち消す方向に変化しようとする現象.
すなわち, 平衡状態にある系に外部からの変化を与えると, 系はその変化の影響を弱める方向に平衡が移動する.
化学平衡は,
「可逆反応の正反応と逆反応の速度が等しくなった状態」である.
したがって, 濃度・温度・圧力などの条件が変わると, それに応じて正反応と逆反応の速度のどちらかが相対的に速くなり,
平衡の位置が変化する(平衡の移動).
濃度の変化による平衡の移動
例:N₂ + 3H₂ ⇄ 2NH₃(ΔH = -92 kJ)
H₂やN₂を加える → 右に移動(NH₃が増加)
NH₃を加える → 左に移動(NH₃が分解される)
H₂やN₂を除く → 左に移動
NH₃を除く → 右に移動
濃度の増減によって, それを打ち消す方向に反応が進む.
温度の変化による平衡の移動
N₂ + 3H₂ ⇄ 2NH₃(ΔH = -92 kJ)
ΔH < 0 → 発熱反応(生成時に熱を放出)
ΔH > 0 → 吸熱反応(生成時に熱を吸収)
温度上昇 → 吸熱方向(ΔH > 0 の反応)が優先
温度下降 → 発熱方向(ΔH < 0 の反応)が優先
すなわち, 温度を上げると左(NH₃分解)に, 温度を下げると右(NH₃生成)に平衡が移動する.
圧力の変化による平衡の移動
N₂ + 3H₂ ⇄ 2NH₃
気体のモル数:左4 mol → 右2 mol
圧力を上げる(体積を小さくする) → モル数の少ない側(右)に移動
圧力を下げる(体積を大きくする) → モル数の多い側(左)に移動
ただし, 固体や液体の成分は体積変化にほとんど影響しないため, 気体成分のみを考慮する.
外部から与えた変化 平衡移動の方向
濃度を増やす 濃度が減少する方向
濃度を減らす 濃度が増加する方向
圧力を上げる 気体の分子数(物質量)が減少する方向
圧力を下げる 気体の分子数(物質量)が増加する方向
温度を上げる 吸熱反応(ΔH > 0)が起こる方向
温度を下げる 発熱反応(ΔH < 0)が起こる方向
触媒を加える 移動しない(平衡に達する時間は短縮)
※ルシャトリエの原理は, 化学変化に限らず,
溶質が溶媒に溶解する溶解平衡や, 気体と液体間の気液平衡などの
物理的変化における平衡にも広く成り立つ.
ルシャトリエの原理は, 化学平衡の法則によっても説明できる.
例:N₂ + 3H₂ ⇄ 2NH₃ ΔH = -92 kJ
[1] 濃度変化と濃度平衡定数 Kc
温度が一定ならば, Kc = [NH₃]² / ([N₂][H₂]³) は一定である.
温度を一定に保ちながら N₂ を加えると [N₂] が増える.
分母が大きくなるため, Kc を一定に保つには分子が大きく(右側生成物が増える)方向に平衡が移動する.
すなわち, [N₂] が減少する方向(右)に移動する.
[2] 圧力変化と圧平衡定数 Kp
温度が一定ならば, Kp = (P_NH₃)² / (P_N₂ × (P_H₂)³) は一定である.
温度を一定に保ちながら密閉容器の体積を半分にすると, 各気体の分圧が2倍になる.
このとき, 分子の次数2の分子項は4倍, 合計次数4の分母項は16倍になる.
よって Kp を一定に保つために, 分子が大きく分母が小さくなる方向(右)に平衡が移動する.
すなわち, 気体の分子数が減少する方向(右)に移動する.
[3] 温度変化と平衡定数 Kc, Kp
発熱反応(ΔH < 0)のとき, 温度が高くなるほど Kc, Kp は小さくなる.
吸熱反応(ΔH > 0)のとき, 温度が高くなるほど Kc, Kp は大きくなる.
例の反応では温度を上げると Kc, Kp の値が元より小さくなる点で新たな平衡に達する.
したがって, 分子が小さく分母が大きくなる方向(左)に平衡が移動する.
すなわち, 吸熱反応(ΔH > 0)の方向に平衡が移動する.
圧力変化と平衡混合気体の色の変化
次の平衡は, 加圧すると右向き(分子数減少)に, 減圧すると左向き(分子数増加)に移動する.
2NO₂(赤褐色) ⇄ N₂O₄(無色)
この平衡混合気体の体積を温度一定で変化させると, 色の変化は次のようになる.
体積を 1/2 にする(加圧)
→ 直後:NO₂ の濃度が一時的に2倍になり, 色が濃くなる
→ 平衡移動後:N₂O₄ が増加し, 色が薄くなる(ただし最初よりはやや濃い)
体積を2倍にする(減圧)
→ 直後:NO₂ の濃度が1/2になり, 一時的に色が薄くなる
→ 平衡移動後:NO₂ が増加し, 色が濃くなる(ただし最初よりやや薄い)
温度一定で体積を小さくすると圧力が増加する.
単純に「N₂O₄ の割合が増えて色が薄くなる」と考えるのは誤りである.
これは, 平衡移動が起こる前に, 体積変化による一時的な濃度変化が起こるためである.
色の濃さは光路中に含まれる NO₂ 分子の数によって決まる.
体積を 1/2 にすると, 単位体積あたりの NO₂ 濃度は2倍になるため, 一時的に色が濃く見える.
その後, N₂O₄ が増える方向に平衡が移動して色が薄くなるが,
最初よりはやや濃い状態で安定する.
平衡移動は「外部からの変化を緩和する」ものであり, 外部変化以上には移動しない.
また, シリンダーを横から見た場合と下から見た場合では, 色の変化の見え方が異なる.
体積を 1/2 にすると, NO₂ 濃度は2倍になるが, 下から見たときの光路長は 1/2 になる.
したがって, 加圧直後には下から見た場合の色は変化しない.
つまり, 下から観察すると, 体積に依存せず NO₂ 濃度の変化のみを観測できる.
次の平衡状態に、かっこ内の条件変化を与えたとき、平衡はどちらに移動するか。
(1) NH₃ + H₂O ⇄ NH₄⁺ + OH⁻ (NaOH を加える)
(2) 2SO₂ + O₂ ⇄ 2SO₃ (加圧する)
(3) H₂ + I₂ ⇄ 2HI (減圧する)
(4) N₂ + 3H₂ ⇄ 2NH₃ ΔH = -92 kJ (加熱する)
(5) 3O₂ ⇄ 2O₃ ΔH = +285 kJ (冷却する)
(6) N₂ + 3H₂ ⇄ 2NH₃ (触媒を加える)
(7) C(固) + H₂O(気) ⇄ CO + H₂ (加圧する)
(8) N₂ + 3H₂ ⇄ 2NH₃ (体積を小さくする)
(9) N₂ + 3H₂ ⇄ 2NH₃ (温度・体積一定でアルゴンを加える)
(10) N₂ + 3H₂ ⇄ 2NH₃ (温度・全圧一定でアルゴンを加える)
解答:
(1) 左に移動 (2) 右に移動 (3) 移動しない (4) 左に移動
(5) 左に移動 (6) 移動しない (7) 左に移動 (8) 右に移動
(9) 移動しない (10) 左に移動
解説:
(1) NaOH を加えると OH⁻ の濃度が増える。
平衡は OH⁻ の濃度が減少する方向(左)に移動する。
→ 共通イオン効果:平衡状態にあるとき、電離で生じたイオンと同じイオンを加えると、
そのイオンが減少する方向に平衡が移動する。
(2) 気体の分子数が減少する方向(右)に移動(左辺3個、右辺2個)。
(3) 両辺とも分子数が2個であるため移動しない。
(4) 吸熱反応(ΔH > 0)が起こる方向(左)に移動する。
(5) 発熱反応(ΔH < 0)が起こる方向(左)に移動する。
(6) 触媒は反応速度を速めるが、平衡自体の位置には影響しない(平衡到達が速くなるだけ)。
(7) 固体は圧力の影響を受けないため、気体の分子数が減少する方向(右)に移動。
(8) 「体積を小さくする」=「加圧する」
→ 気体の分子数が減少する方向(右)に移動(左辺4個、右辺2個)。
(9) Ar は反応に関係しない。
体積・温度一定 → 濃度も圧力も変化しない → 平衡移動しない。
(10) 全圧一定で Ar を加えると、反応気体の分圧の合計が減少。
→ 減圧に相当 → 気体の分子数が増加する方向(左)に移動。
アンモニア NH₃ を合成するには、次の平衡を右に移動させる必要がある。
N₂(気) + 3H₂(気) ⇄ 2NH₃(気) ΔH = −92 kJ
発熱反応なので、低温にすると右に移動する。
右辺の方が分子数が少ないため、高圧にすると右に移動する。
したがって、ルシャトリエの原理から見ると「低温・高圧条件」が望ましい。
しかし、低温すぎると反応速度が遅く進行しない。
また、高圧すぎると反応容器が破損する危険がある。
そこでハーバーらは数千種の物質の中から適切な触媒を発見し、
反応速度の低下を防ぐことに成功した。
ボッシュは特殊な二重構造反応容器を開発し、高圧に耐える装置を完成させた。
最終的に、
400〜600 °C、1×10⁷〜3×10⁷ Pa(約100〜300気圧)、触媒 Fe₃O₄
によって工業的にアンモニアを合成することができた。
反応時には Fe₃O₄ が H₂ で還元され、生成した Fe が触媒作用を示す。
生成した NH₃ は冷却によって液化し、 N₂ や H₂ から分離される。
(NH₃ は N₂ や H₂ よりも容易に液化する。)
20世紀初頭、人類は人口増加に伴う食糧不足に直面していた。
これを解決するために、窒素肥料の原料となる NH₃ の合成が化学者の最大の課題だった。
空気中の大量の N₂ を化学的に固定する――いわゆる「空中窒素の固定」が目標だった。
しかし N₂ は強固な三重結合 N≡N をもつため、非常に反応しにくい。
ルシャトリエの原理と触媒の発見によって、工業化が可能となった。
ハーバー・ボッシュ法は窒素肥料の大量生産を可能にし、
「空気からパンを作る」と呼ばれるほど人類史に残る発明となった。
一方で、窒素化合物は爆薬の原料にもなるため、
第一次世界大戦を長引かせたという負の側面もある。
ハーバー・ボッシュ法の開発は、化学史だけでなく人類史上の大事件である。