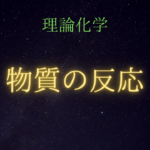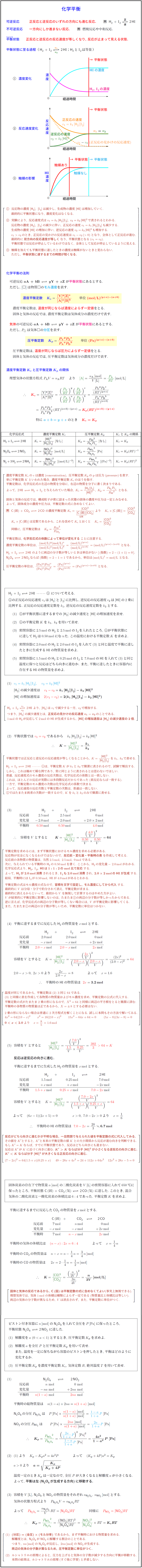
可逆反応
正反応と逆反応のいずれの方向にも進む反応。
不可逆反応
一方向にしか進まない反応。例: 燃焼反応や中和反応。
平衡状態
正反応と逆反応の反応速度が等しくなり,反応が見かけ上止まって見える状態。
平衡状態に至る過程(例: H2 + I2 ⇄ 2HI)
(1) 濃度変化
反応物の濃度 (H2, I2) は減少し,生成物の濃度 (HI) は増加していく。
最終的に平衡状態になり,濃度変化はなくなる。
(2) 反応速度変化
実験により,反応速度式は
v1 = k1・[H2]・[I2]
v2 = k2・[HI]^2
で表されるとわかる。
反応物の濃度 [H2],[I2] が減少すると,正反応の速度 v1 も減少する。
生成物の濃度 [HI] が増加すると,逆反応の速度 v2 も増加する。
v1 > v2 のとき,正反応の見かけの反応速度は (v1 − v2) (>0) となり,全体として正反応が進む。
最終的に v1 = v2 となり,平衡状態になる。
平衡状態でも,実際には正反応・逆反応ともに起き続けているが,全体として変化が止まっているように見える。
(3) 触媒の影響
触媒を加えても,平衡状態に達したときの各物質の濃度は変わらない。
ただし,平衡状態に達するまでの時間が短くなる。
――――
化学平衡の法則
可逆反応
aA + bB ⇄ yY + zZ
が平衡状態にあるとする。ここで [A] は物質Aのモル濃度。
濃度平衡定数
Kc = ( [Y]^y ・ [Z]^z ) / ( [A]^a ・ [B]^b )
単位: (mol/L)^( y+z-(a+b) )
濃度平衡定数は,温度が一定ならば,初期濃度によらず一定値になる。
固体と気体の反応では,濃度平衡定数は気体成分の濃度だけで表す(固体は入れない)。
気体の可逆反応
aA + bB ⇄ yY + zZ
が平衡状態にあるとする。ここで P(A) は気体Aの分圧。
圧平衡定数
Kp = ( P(Y)^y ・ P(Z)^z ) / ( P(A)^a ・ P(B)^b )
単位: (Pa)^( y+z-(a+b) )
圧平衡定数は,温度が一定ならば,全圧によらず一定値になる。
固体と気体の反応では,圧平衡定数も気体成分の分圧だけで表す(固体は入れない)。
濃度平衡定数 Kc と 圧平衡定数 Kp の関係
理想気体の状態方程式 PV = nRT より,
濃度 [A] = n(A)/V = P(A)/(R・T) と書ける。
この結果から,
Kc = Kp ・ (R・T)^( (a+b) − (y+z) )
特に a+b = y+z のとき,Kc = Kp になる。
例(反応式 / Kc / Kp / 両者の関係)
H2 + I2 ⇄ 2HI
Kc = [HI]^2 / ( [H2]・[I2] ) 単位なし
Kp = P(HI)^2 / ( P(H2)・P(I2) ) 単位なし
関係: Kc = Kp
N2O4 ⇄ 2NO2
Kc = [NO2]^2 / [N2O4] 単位 mol/L
Kp = P(NO2)^2 / P(N2O4) 単位 Pa
関係: Kc = Kp・(R・T)^(-1)
N2 + 3H2 ⇄ 2NH3
Kc = [NH3]^2 / ( [N2]・[H2]^3 ) 単位 (mol/L)^(-2)
Kp = P(NH3)^2 / ( P(N2)・P(H2)^3 ) 単位 (Pa)^(-2)
関係: Kc = Kp・(R・T)^(2)
補足
・「Kc」の c は concentration(濃度),「Kp」の p は pressure(圧力)。
・授業などで単に「平衡定数 K」と言ったら,普通は Kc を指す。
・平衡定数は「左辺の物質を分母,右辺の物質を分子」に書く決まり。
例えば 2HI ⇄ H2 + I2 のときは
Kc = [H2][I2] / [HI]^2
Kp = P(H2)・P(I2) / P(HI)^2
・固体を含む反応では,固体は濃度・圧力がほぼ一定なので,式に入れない。
例: C(s) + CO2(g) ⇄ 2CO(g)
本当は Kc = [CO]^2 / ( [C(s)]・[CO2] ) だが [C(s)] は一定なので,
C(s)をまとめて定数に吸収し,実用上は
Kc = [CO]^2 / [CO2]
同様に Kp = P(CO)^2 / P(CO2)
・平衡定数の単位は,反応式の係数から決まる。
濃度平衡定数の単位は (mol/L)^( y+z-(a+b) )。
H2 + I2 ⇄ 2HI の場合,指数は 2 − (1+1) = 0 なので単位なし。
N2O4 ⇄ 2NO2 の場合,指数は 2 − 1 = 1 なので単位 mol/L。
圧平衡定数では同様に (Pa)^( y+z-(a+b) ) となる。
――――
演習 (H2 + I2 ⇄ 2HI を例にする)
反応の速さ
正方向の反応速度を v1,逆方向の反応速度を v2 とすると
v1 = k1・[H2]・[I2]
v2 = k2・[HI]^2
(1) 平衡に達するまでの [H2] の減少速度と [HI] の増加速度
[H2] は v1 で消費される一方,逆反応 v2 で生成もするので,
見かけの [H2] の減少速度は (v1 − v2)。
HI は H2 1 mol あたり 2 mol できるので,
見かけの [HI] の増加速度は 2×(v1 − v2)。
(2) 平衡状態では v1 = v2。
よって k1・[H2]・[I2] = k2・[HI]^2。
これを並べ替えると
K = [HI]^2 / ( [H2]・[I2] ) = k1 / k2。
この反応では K が速度定数の比だけで書ける。ただしこれはかなり特別なケース。
(3) 2.5 mol の H2 と 2.5 mol の I2 を密閉容器に入れた。
平衡では H2 が 0.50 mol になった。
すると H2 は 2.0 mol 減少したことになる。
H2 : I2 : HI = 1 : 1 : 2 なので
I2 も 2.0 mol 減少し,HI が 4.0 mol 生成した。
容積を V L とすると,
[H2] = 0.50 / V
[I2] = 0.50 / V
[HI] = 4.0 / V
よって
K = [HI]^2 / ( [H2]・[I2] )
= (4.0/V)^2 / ( (0.50/V)・(0.50/V) )
= 64
この反応では左右の分子数が同じなので V が約分で消え,K に単位はつかない。
(4) 2.0 mol の H2 と 2.0 mol の I2 を入れて,同じ温度で平衡に達した場合。
平衡までに反応した H2 の量を x mol とおくと
平衡時
H2 : 2.0 − x
I2 : 2.0 − x
HI : 2x
同じく容積を V L とすると
K = ( (2x)/V )^2 / ( (2.0−x)/V ・ (2.0−x)/V ) = 64
整理すると (2x)/(2.0−x) = 8 になり,x = 1.6 mol。
よって平衡時の HI の量は 2x = 3.2 mol。
(5) 最初に
H2 = 1.5 mol
I2 = 0.25 mol
HI = 7.0 mol
を同じ温度で入れる。
まず,この状態の
Q = [HI]^2 / ( [H2]・[I2] )
(※これは「いまの比」。Kと比べるための値)
を計算する。容積を V L とすると
Q = (7.0/V)^2 / ( (1.5/V)・(0.25/V) )
= 392/3
これは 64 より大きいので,Q > K。
Q > K のとき,反応は逆方向(HI → H2 + I2 方向)に進む。
では,逆方向に x mol 進んだとする。
すると平衡時
H2 : 1.5 + x
I2 : 0.25 + x
HI : 7.0 − 2x
これを K = 64 に代入して x を解くと,
x = 1/6 mol。
したがって平衡時の HI は
7.0 − 2x = 7.0 − 2/6 = 20/3 ≒ 6.7 mol。
――――
固体 C と CO2 の反応
C(s) + CO2(g) ⇄ 2CO(g)
二酸化炭素 CO2 を n mol, 体積 V L の密閉容器に入れ,固体炭素を加えて高温で平衡にしたところ,
混合気体の体積比 (CO2 : CO) が 6 : 4 だったとする。
気体は理想気体とみなすと,体積比 = 物質量比。
CO2 : CO = 6 : 4 = (3 : 2)。
よって平衡時
CO2 = (3/4)n mol
CO = (1/2)n mol
K = [CO]^2 / [CO2]
= ( ( (1/2)n ) / V )^2 / ( ( (3/4)n ) / V )
= n / (3V)
この平衡では左辺に固体 C があるが,固体は一定なので式に含めない。
この場合は左と右で気体分子数が変わるので,K に単位 (mol/L) がつくし,V も残る。
――――
N2O4 ⇄ 2NO2 の平衡と解離度
ピストン付き容器に N2O4 を n mol 入れ,全圧を P Pa に保って平衡にした。
N2O4 のうち a (0 < a < 1) が NO2 に解離したとする(これを解離度 a という)。
平衡時の物質量
N2O4 : n(1−a)
NO2 : 2na
全体の物質量は n(1+a)。
分圧は「全圧 × モル分率」なので
P(N2O4) = P × ( n(1−a) / n(1+a) ) = P × (1−a)/(1+a)
P(NO2) = P × ( 2na / n(1+a) ) = P × (2a)/(1+a)
よって
Kp = P(NO2)^2 / P(N2O4)
= { [ P × (2a)/(1+a) ]^2 } / { P × (1−a)/(1+a) }
= (4a^2 / (1−a^2)) × P
これを a について解くと
(Kp + 4P) a^2 = Kp
a = sqrt( Kp / (Kp + 4P) )
温度が一定なら Kp は一定。
P を大きくすると a は小さくなる。
つまり,圧力を上げると N2O4 側(分子数が少ない側)に平衡がずれる。
これはルシャトリエの原理「圧力を上げると,気体分子数の少ない側に平衡が移動する」と一致する。
さらに,理想気体の式 PV = nRT から
P(A) = [A]・R・T
が成り立つので
Kp = Kc ・ R ・ T^( (y+z)-(a+b) )
この反応では
Kp = Kc ・ R ・ T
になる。