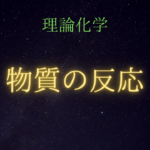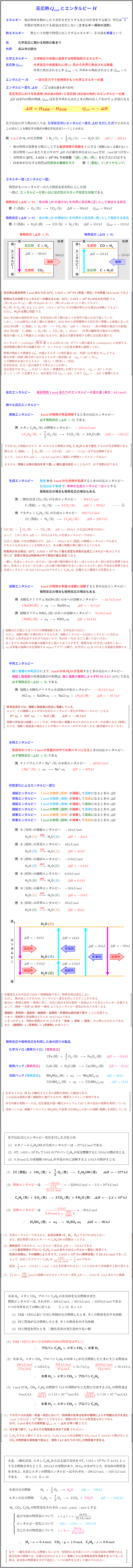
最後、H₂は0.40mol、C₂H₆は0.60mol (有効数字2桁)の誤りである。
エネルギー 他の物体を動かしたり変形させたりするなどの仕事をする能力. 単位はJ(ジュール).
形態が変換されても総量は変化しない(エネルギー保存の法則).
熱エネルギー 熱という形態で物質に出入りするエネルギー. その量を熱量という.
系 化学反応に関わる物質の集まり.
外界 系以外の部分.
化学エネルギー 化学結合や状態に由来する物質固有のエネルギー.
反応熱Qout 化学反応や状態変化に伴い, 系から外界に放出される熱量.
外界に放出されるとき Qout>0, 外界から吸収されるとき Qout<0.
エンタルピーH 一定の圧力下で各物質がもつ化学エネルギーの量.
エンタルピー変化ΔH(Δは変化量を表す記号).
定圧反応における生成物(反応後の物質)と反応物(反応前の物質)のエンタルピーの差.
ΔHは系内の熱の増減, Qoutは系を外界から見たときの熱の出入りなので±が逆になる.
ΔH = H生成物 − H反応物 Qout = −ΔH
化学反応に伴う熱の出入りは, 化学反応式にエンタルピー変化ΔHを付した式で示される.
この式のことを熱化学方程式や熱化学反応式ということがある.
例 1molのH₂の完全燃焼
1H₂(気) + 1/2O₂(気) → H₂O(液) ΔH = −286kJ
・他の物質の係数を分数にしてでも着目物質の係数を1にする(実際には1は書かない).
・着目物質1molあたりを示すのでΔHの単位はkJ/molだが, /molは省略する.
・各物質の25℃, 1.013×10⁵Paでの状態(固, 液, 気)を化学式に付記する.
・同素体が存在する物質は同素体の種類を示す. 例:C(黒鉛), C(ダイヤモンド)
エネルギー図(エンタルピー図)
物質がもつエンタルピーの大小関係を相対的に示した図.
一般に, エンタルピーが高いほど反応性が大きい不安定な状態である.
発熱反応(ΔH<0) 系の熱(Hの減少分)を外界に反応熱(正)として放出する反応.
例 C(黒鉛) + O₂(気) → CO₂(気) ΔH = −394kJ Qout = 394kJ.
吸熱反応(ΔH>0) 系の熱(Hの増加分)を外界から反応熱(負)として吸収する反応.
例 C(黒鉛) + H₂O(液) → CO(気) + H₂(気) ΔH = 131kJ Qout = −131kJ.
熱化学の視点と表現の違い
反応熱は着目物質1molあたりの25℃, 1.013×10⁵Pa(常温・常圧)での熱量(kJ/mol)である.
物質はその状態でエンタルピーが異なるため, 25℃, 1.013×10⁵Paのものを付記する.
(気)はgasの(g), (液)はliquidの(l), (固)はsolidの(s)と表してもよい.
H₂(気)やO₂(気)のように状態が明らかな場合は省略できるが, H₂Oは常に付記する.
2021年以前の高校化学では, 化学反応に伴う熱の出入りを等号で結んだ式で表していた.
しかし, これは時代に遅れた表現であり, 2022年からは世界標準・大学化学に準拠した形となった.
2022年以降:C(黒鉛) + O₂(気) → CO₂(気) ΔH = −394kJ (系の物質の視点)
2021年以前:C(黒鉛) + O₂(気) = CO₂(気) + 394kJ (外界の観察者の視点)
視点の違いにより熱量の±が逆になるため, 過去の文献を使用する際には注意が必要.
エンタルピー(enthalpy)(熱含量とも呼ばれる)は, ギリシャ語の「温まる」(enthalpein)に由来する.
熱力学との関係
物質が吸収した熱量をQin, 内部エネルギーの変化量をΔU, 外部への仕事をWoutとする.
熱力学第一法則(エネルギー保存則)は
Qin = ΔU + Wout.
これをお金のたとえで言えば
(収入) = (貯金) + (支出).
化学反応は一般に圧力一定で進行するため,
定圧条件ではWout = PΔV(圧力×体積変化)なので
Qin = ΔU + PΔV.
H = U + PVと定義すると, 定圧変化では
Qin = ΔH, つまりQout = −ΔH
と簡潔に表せる.
反応エンタルピーとその種類
反応エンタルピー 着目物質1molあたりのエンタルピー変化量(単位:kJ/mol).
燃焼エンタルピー
1molの物質が完全燃焼するときの反応エンタルピー.
必ず発熱反応(ΔH<0)である.
例:エタンC₂H₆(気)の燃焼エンタルピー −1561kJ/mol.
C₂H₆(気) + 7/2O₂(気) → 2CO₂(気) + 3H₂O(液) ΔH = −1561kJ.
完全燃焼とは, C, H, Oを含む物質がCO₂とH₂Oにまで変化する燃焼.
C(黒鉛) + 1/2O₂(気) → CO(気) ΔH = −111kJ は不完全燃焼である.
したがって, これはC(黒鉛)の燃焼エンタルピーではない.
燃焼とは熱の放出を伴う激しい酸化還元反応であり, 必ず発熱反応である.
生成エンタルピー
単体から1molの化合物が生成するときの反応エンタルピー.
左辺は必ず単体で, 単体の生成エンタルピーは0とする.
発熱反応の場合も吸熱反応の場合もある.
例:CO₂(気)の生成エンタルピー −394kJ/mol.
C(黒鉛) + O₂(気) → 1CO₂(気) ΔH = −394kJ.
例:C₂H₂(気)の生成エンタルピー 226.7kJ/mol.
2C(黒鉛) + H₂(気) → 1C₂H₂(気) ΔH = 226.7kJ.
CO(気) + 1/2O₂(気) → CO₂(気) ΔH = −283kJ の左辺は単体でないため, これはCO₂の生成エンタルピーではない.
また, C(黒鉛) + O₂(気) → CO₂(気) はCの完全燃焼なので, ΔH = −394kJ はCの燃焼エンタルピーでもある.
同素体がある場合, 25℃, 1.013×10⁵Paで最も安定な状態の生成エンタルピーを0とする.
炭素の場合は黒鉛が最も安定である.
一般に, 生成エンタルピーが小さい(負の値で絶対値が大きい)ほど物質は安定で,
正の値で絶対値が大きいほど不安定.
生成エンタルピーが226.7kJ/molのアセチレンC₂H₂は, 圧縮すると爆発する性質をもつ.
溶解エンタルピー
1molの物質が多量の溶媒に溶解するときの反応エンタルピー.
発熱反応の場合も吸熱反応の場合もある.
例:NaOH(固)の溶解エンタルピー −44.5kJ/mol.
1NaOH(固) + aq → NaOH(aq) ΔH = −44.5kJ.
例:KNO₃(固)の溶解エンタルピー 34.9kJ/mol.
1KNO₃(固) + aq → KNO₃(aq) ΔH = 34.9kJ.
溶解は化学反応ではなく物理現象だが, 熱の出入りがあるためエンタルピー変化で表す.
NaOH + H₂O のように書かず, NaOH(aq) の形で示す.
aqはaqua(水溶液)を意味する.
中和エンタルピー
酸と塩基の中和反応により, 1molのH₂Oが生成するときの反応エンタルピー.
強酸と強塩基の希薄溶液の中和熱は酸や塩基の種類によらず約56.5kJ(25℃).
必ず発熱反応(ΔH<0)である.
例:HCl(aq) + NaOH(aq) → NaCl(aq) + 1H₂O(液) ΔH = −56.5kJ.
希薄溶液では強酸と強塩基は完全電離しているため,
反応は H⁺(aq) + OH⁻(aq) → H₂O(液) ΔH = −56.5kJ.
弱酸や弱塩基では電離にエネルギーが必要(吸熱)なため, 中和エンタルピーの絶対値はやや小さくなる.
水和エンタルピー
気体状のイオン1molが多量の水中で水和イオンになるときの反応エンタルピー.
必ず発熱反応(ΔH<0)である.
例:Na⁺(気) + aq → Na⁺(aq) ΔH = −403kJ.
状態変化によるエンタルピー変化
凝縮エンタルピー 1molの物質(気体)が凝縮して液体になるときのΔH.
蒸発エンタルピー 1molの物質(液体)が蒸発して気体になるときのΔH.
凝固エンタルピー 1molの物質(液体)が凝固して固体になるときのΔH.
融解エンタルピー 1molの物質(固体)が融解して液体になるときのΔH.
凝華エンタルピー 1molの物質(気体)が凝華して固体になるときのΔH.
昇華エンタルピー 1molの物質(固体)が昇華して気体になるときのΔH.
例:H₂O(気) → H₂O(液) 凝縮エンタルピー −44kJ/mol.
H₂O(液) → H₂O(気) 蒸発エンタルピー 44kJ/mol.
H₂O(液) → H₂O(固) 凝固エンタルピー −6.0kJ/mol.
H₂O(固) → H₂O(液) 融解エンタルピー 6.0kJ/mol.
H₂O(気) → H₂O(固) 凝華エンタルピー −50kJ/mol.
H₂O(固) → H₂O(気) 昇華エンタルピー 50kJ/mol.
状態変化は化学反応ではなく物理現象だが, 熱が出入りするためエンタルピー変化で表す.
液体→気体は固体→液体より大きなエネルギーを要する.
したがって蒸発熱の方が融解熱より大きい.
凝縮熱・蒸発熱・凝固熱・融解熱・凝華熱・昇華熱は絶対値で表す.
つまり凝縮熱と蒸発熱はいずれも44kJ/molである.
また, (融解熱)+(蒸発熱)=(昇華熱)が成り立つ.
発熱反応・吸熱反応の応用例
化学カイロ(携帯カイロ):発熱反応
2Fe(固) + 3/2O₂(気) → Fe₂O₃(固) ΔH = −824kJ.
発熱パック:発熱反応
CaO(固) + H₂O(液) → Ca(OH)₂(固) ΔH = −65kJ.
冷却パック:吸熱反応
NH₄NO₃(固) + aq → NH₄NO₃(aq) ΔH = 26kJ.
CO(NH₂)₂(固) + aq → CO(NH₂)₂(aq) ΔH = 15kJ.
化学カイロは鉄が酸化するときの発熱を利用したもので, ゆっくり進行するため持続的に温かい.
弁当の発熱パックはCaOと水の反応による急速な発熱を利用する.
冷却パックは硝酸アンモニウムや尿素の溶解吸熱を利用している.
水素H₂, メタンCH₄, プロパンC₃H₈の各気体を完全燃焼させた.
燃焼エンタルピーはそれぞれ −286kJ/mol, −891kJ/mol, −2219kJ/molである.
3つの気体を以下の順に並べよ.
C = 12, H = 1.0
(1) 同温・同圧において同じ体積が完全燃焼したとき, 多くの熱量を出す気体の順.
同温・同圧において同体積の気体の物質量は等しい.
したがって, プロパンC₃H₈ > メタンCH₄ > 水素H₂.
(2) 同じ質量が完全燃焼したとき, 多くの熱量を出す気体の順.
水素H₂, メタンCH₄, プロパンC₃H₈の気体1gが完全燃焼したときに生じる熱量はそれぞれ
286kJ/mol ÷ 2.0g/mol = 143kJ/g,
891kJ/mol ÷ 16g/mol = 55.7kJ/g,
2219kJ/mol ÷ 44g/mol = 50.4kJ/g.
したがって, 水素H₂ > メタンCH₄ > プロパンC₃H₈.
(3) 同じ熱量を得たとき, 二酸化炭素の発生量が少ない順.
1molのH₂, CH₄, C₃H₈の燃焼で1kJの発熱が生じた際に生成するCO₂の物質量はそれぞれ
0mol/kJ,
1mol/891kJ ≒ 1.12×10⁻³mol/kJ,
3mol/2219kJ ≒ 1.35×10⁻³mol/kJ.
したがって, 水素H₂ < メタンCH₄ < プロパンC₃H₈.
(参考)
(1) アボガドロの法則:同温・同圧において, 同体積の気体は種類によらず同数の分子を含む.
したがって, 個数が同じなら物質量も等しい.
1molあたりの発熱量Qout = −ΔHが多い順に並ぶ.
(2) 1gあたりの発熱量を求めるには, 分子量で割って比較する.
(3) C₃H₈分子はCを3個含むから, 1molの完全燃焼でCO₂を3mol発生し, 2219kJの熱を生じる.
CO₂の発生mol数を発熱量で割ると, 1kJあたりのCO₂生成量が求まる.
混合気体の燃焼(H₂・CO₂・C₂H₆の例)
水素, 二酸化炭素, エタンC₂H₆からなる混合気体を0℃, 1.013×10⁵Paで44.8Lとったところ, 完全燃焼させると1051kJの発熱があり, 39.6gの水が生じた.
各気体の物質量を求めよ.
水素とエタンの燃焼エンタルピーはそれぞれ −286kJ/mol, −1561kJ/molである.
H = 1.0, O = 16.
水素の完全燃焼
H₂ + 1/2O₂ → H₂O ΔH = −286kJ
エタンの完全燃焼
C₂H₆ + 7/2O₂ → 2CO₂ + 3H₂O ΔH = −1561kJ
H₂, CO₂, C₂H₆の物質量をそれぞれ x, y, z mol とすると,
混合気体の物質量について:
x + y + z = 44.8L / 22.4L/mol = 2mol.
エンタルピー変化について:
−286x −1561z = −1051kJ.
生じた水の物質量について:
x + 3z = 39.6g / 18g/mol = 2.2mol.
この3つの式を連立して解くと,
x = 0.4mol, y = 1.0mol, z = 0.6mol.
したがって, H₂ : 0.4mol, CO₂ : 1.0mol, C₂H₆ : 0.6mol.
(補足)
二酸化炭素CO₂は燃焼しないので, 実質的には水素とエタンの混合気体の燃焼である.
混合気体の燃焼では, 正確な比を求めるために気体ごとに化学反応式を立て,
条件式(体積・発熱量・生成物の量など)を用いて連立するのが基本である.