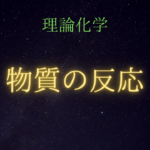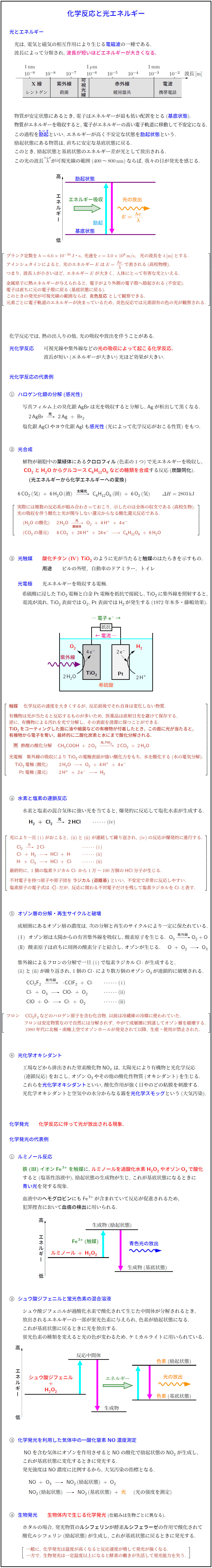
光は, 電気と磁気の相互作用により生じる電磁波の一種である.
波長によって分類され, 波長が短いほどエネルギーが大きくなる.
物質が安定状態にあるとき, 電子はエネルギーが最も低い配置をとる(基底状態).
物質がエネルギーを吸収すると, 電子がエネルギーの高い電子軌道に移動して不安定になる.
この過程を励起といい, エネルギーが高く不安定な状態を励起状態という.
励起状態にある物質は, 直ちに安定な基底状態に戻る.
このとき, 励起状態と基底状態のエネルギー差が光として放出される.
この光の波長λが可視光線の範囲(400〜800 nm)ならば, 我々の目が発光を感じる.
プランク定数を h = 6.6×10⁻³⁴ J·s, 光速を c = 3.0×10⁸ m/s, 光の波長を λ [m] とする.
アインシュタインによると, 光のエネルギー E は E = hc/λ で表される(高校物理).
つまり, 波長 λ が小さいほど, エネルギー E が大きく, 人体にとって有害な光といえる.
金属原子に熱エネルギーが与えられると, 電子がより外側の電子殻へ励起される(不安定).
電子は直ちに元の電子殻に戻る(基底状態に戻る).
このときの発光が可視光線の範囲ならば, 炎色反応として観察できる.
元素ごとに電子軌道のエネルギーが決まっているため, 炎色反応では元素固有の色の光が観察される.
化学反応では, 熱の出入りの他, 光の吸収や放出を伴うことがある.
光化学反応 可視光線や紫外線などの光の吸収によって起こる化学反応.
波長が短い(エネルギーが大きい)光ほど効果が大きい.
光化学反応の代表例
① ハロゲン化銀の分解(感光性)
写真フィルム上の臭化銀 AgBr は光を吸収すると分解し, Ag が析出して黒くなる.
2AgBr → 2Ag + Br₂
塩化銀 AgCl やヨウ化銀 AgI も感光性(光によって化学反応がおこる性質)をもつ.
② 光合成
植物が細胞中の葉緑体にあるクロロフィル(色素の1つ)で光エネルギーを吸収し,
CO₂ と H₂O からグルコース C₆H₁₂O₆ などの糖類を合成する反応(炭酸同化).
(光エネルギーから化学エネルギーへの変換)
6CO₂(気) + 6H₂O(液) →[太陽光] C₆H₁₂O₆(固) + 6O₂(気) ΔH = 2803 kJ
実際には複数の反応系が組み合わさっておこり, 示したのは全体の収支である(高校生物).
光の吸収を伴う酸化と光が関与しない還元からなる酸化還元反応である.
(H₂Oの酸化) 2H₂O →[光][葉緑体] O₂ + 4H⁺ + 4e⁻
(CO₂の還元) 6CO₂ + 24H⁺ + 24e⁻ → C₆H₁₂O₆ + 6H₂O
③ 光触媒
酸化チタン(IV) TiO₂ のように光が当たると触媒のはたらきを示すもの.
用途 ビルの外壁, 自動車のドアミラー, トイレ
光電極 光エネルギーを吸収する電極.
希硫酸に浸した TiO₂ 電極と白金 Pt 電極を抵抗で接続し, TiO₂ に紫外線を照射すると,
電流が流れ, TiO₂ 表面では O₂, Pt 表面では H₂ が発生する(1972年 本多・藤嶋効果).
触媒 化学反応の速度を大きくするが, 反応前後でそれ自身は変化しない物質.
有機物は光が当たると反応するものが多いため, 医薬品は直射日光を避けて保存する.
逆に, 有機物による汚れを光で分解し, その表面を清潔に保つことができる.
TiO₂ をコーティングした面に油や細菌などの有機物が付着したとき, この面に光が当たると,
有機物から電子を奪い, 最終的に二酸化炭素と水にまで酸化分解される.
例:酢酸の酸化分解
CH₃COOH + 2O₂ →[光, TiO₂] 2CO₂ + 2H₂O
光電極 紫外線の吸収により TiO₂ の電極表面が強い酸化力をもち, 水を酸化する(水の電気分解).
TiO₂電極(酸化):2H₂O → O₂ + 4H⁺ + 4e⁻
Pt電極(還元):2H⁺ + 2e⁻ → H₂
④ 水素と塩素の連鎖反応
水素と塩素の混合気体に強い光を当てると, 爆発的に反応して塩化水素が生成する.
H₂ + Cl₂ →[光] 2HCl …(iv)
光により一旦(i)がおこると, (ii)と(iii)が連続して繰り返され, (iv)の反応が爆発的に進行する.
Cl₂ →[光] 2Cl· (i)
Cl· + H₂ → HCl + H· (ii)
H· + Cl₂ → HCl + Cl· (iii)
最終的に, 1個の塩素ラジカル Cl· から 1万〜100万個の HCl 分子が生じる.
不対電子を持つ原子や原子団をラジカル(遊離基)といい, 不安定で非常に反応しやすい.
塩素ラジカルは Cl· のように表される.
⑤ オゾン層の分解・再生サイクルと破壊
成層圏にあるオゾン層の濃度は, 次の分解と再生のサイクルにより一定に保たれている.
(I) オゾン層は太陽からの有害紫外線を吸収し, 酸素原子を生じる. O₃ →[紫外線] O₂ + O
(II) 酸素原子は直ちに周囲の酸素分子と結合し, オゾンが生じる. O + O₂ → O₃
紫外線によるフロンの分解で一旦(i)で塩素ラジカル Cl· が生成すると,
(ii)と(iii)が繰り返され, 1個の Cl· により数万個の O₃ が連鎖的に破壊される.
CCl₂F₂ →[紫外線] ·CClF₂ + Cl· (i)
Cl· + O₃ → ClO· + O₂ (ii)
ClO· + O· → Cl· + O₂ (iii)
フロン CCl₂F₂ などのハロゲン原子を含む化合物. 以前は冷蔵庫の冷媒に使われていた.
フロンは安定物質なので自然には分解されず, やがて成層圏に到達してオゾン層を破壊する.
1980年代に北極・南極上空でオゾンホールが発見されて以降, 生産・使用が禁止された.
⑥ 光化学オキシダント
工場などから排出された窒素酸化物 NOx は, 太陽光により有機物と光化学反応(連鎖反応)をおこし,
オゾン O₃ やその他の酸化性物質(オキシダント)を生じる.
これらを光化学オキシダントといい, 酸化作用が強く目やのどの粘膜を刺激する.
光化学オキシダントと空気中の水分からなる霧を光化学スモッグという(大気汚染).
化学発光 化学反応に伴って光が放出される現象.
化学発光の代表例
① ルミノール反応
鉄(III)イオン Fe³⁺ を触媒に, ルミノールを過酸化水素 H₂O₂ やオゾン O₃ で酸化すると,
(塩基性溶液中) 励起状態の生成物が生じ, これが基底状態になるときに青い光を発する現象.
血液中のヘモグロビンにも Fe³⁺ が含まれていて反応が促進されるため, 犯罪捜査において血痕の検出に用いられる.
ルミノール + H₂O₂ → 生成物(励起状態) → 生成物(基底状態) + 青色光
② シュウ酸ジフェニルと蛍光色素の混合溶液
シュウ酸ジフェニルが過酸化水素で酸化されて生じた中間体が分解されるとき,
放出されるエネルギーの一部が蛍光色素に与えられ,色素が励起状態になる.
これが基底状態に戻るときに光を放出する.
蛍光色素の種類を変えると光の色が変わるため, ケミカルライトに用いられている.
③ 化学発光を利用した気体中の一酸化窒素 NO 濃度測定
NO を含む気体にオゾンを作用させると NO の酸化で励起状態の NO₂ が生成し,
これが基底状態に変化するときに発光する.
発光強度は NO 濃度に比例するから, 大気汚染の指標となる.
NO + O₃ → NO₂(励起状態) + O₂
NO₂(励起状態) → NO₂(基底状態) + 光 (光の強度を測定)
④ 生物発光
生物体内で生じる化学発光(仕組みは生物ごとに異なる).
ホタルの場合, 発光物質のルシフェリンが酵素ルシフェラーゼの作用で酸化されて
酸化ルシフェリン(励起状態)が生成し, これが基底状態に戻るときに発光する.
一般に, 化学発光は温度が高くなると反応速度が増して発光が強くなる.
一方で, 生物発光は一定温度以上になると酵素の働きが失活して発光能力を失う.