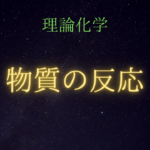難溶性塩の溶解平衡と溶解度積
溶解平衡とは、単位時間に溶解する粒子数と析出する粒子数が等しくなり, 見かけ上溶解も析出も起こっていないように見える状態のこと。
飽和溶液中では沈殿とイオンの間で溶解平衡が成立している。
溶解平衡における平衡定数を「溶解度積」(Solubility Product)という。
温度が一定ならば溶解度積は一定である。
例:塩化銀の溶解平衡
AgCl(固) ⇄ Ag⁺ + Cl⁻
化学平衡の法則より
K = [Ag⁺][Cl⁻] / [AgCl(固)] = (一定)
[AgCl(固)]も一定とみなせるから
K × [AgCl(固)] = [Ag⁺][Cl⁻] = (一定)
これを Ksp = [Ag⁺][Cl⁻] とまとめて「溶解度積」という。
難溶性塩 AaBb が
AaBb(固) ⇄ aAⁿ⁺ + bBᵐ⁻
の平衡にあるとき、
溶解度積 Ksp = [Aⁿ⁺]ᵃ [Bᵐ⁻]ᵇ
例:クロム酸銀
Ag₂CrO₄(固) ⇄ 2Ag⁺ + CrO₄²⁻
Ksp = [Ag⁺]² [CrO₄²⁻]
AgClは沈殿するから、普通は
Ag⁺ + Cl⁻ → AgCl↓
と表すことが多い。
しかし、厳密には難溶性の塩であっても全く水に溶けないわけではない。
ごくわずかに水に溶けて飽和水溶液となっている。
このとき溶けた溶質はほぼ完全に電離しており、溶解平衡が成立している。
難溶性塩では固体の濃度はほぼ変わらず一定とみなせる。
結局、溶解度積とは「溶解平衡の状態にあるときの各イオンのモル濃度の積」である。
溶解度積と沈殿の生成判定
溶液中の現在の各イオンのモル濃度の積 Qsp と溶解度積 Ksp を比較する。
判定式 状態 結果
Qsp > Ksp 過飽和 沈殿する(過飽和) → 沈殿が生じて平衡へ移行 → Qsp = Ksp
Qsp = Ksp 飽和 平衡状態(飽和)
Qsp < Ksp 不飽和 沈殿しない(不飽和)
AgClの例での説明
AgClの場合、
Qsp = [現在のAg⁺][現在のCl⁻]
Ksp = [平衡状態のAg⁺][平衡状態のCl⁻] = (定数)
Qsp > Ksp のとき、溶解平衡は Qsp = Ksp となる方向に移動する。
つまり [Ag⁺][Cl⁻] を小さくするために AgCl(固) ⇄ Ag⁺ + Cl⁻ の平衡は左に移動する。
平衡移動によって自然に [Ag⁺][Cl⁻] = Ksp の状態に達する。
沈殿が存在するとき、上澄み液は飽和状態であり Qsp = Ksp が成立している。
一方 Qsp < Ksp のときは、沈殿が存在せず、全ての溶質がイオン状態で溶けている。
この場合、自然に飽和状態には到達しないため沈殿は生じない。
一般に、溶解度積が小さい塩ほど沈殿を生じやすく(水に溶けにくい)。
溶解度積は飽和溶液中で存在できるイオンの最大限界濃度を表す。
共通イオン効果
ある電解質の水溶液に、同じ種類のイオンを生じる別の物質を加えると、
ルシャトリエの原理(平衡は外部からの変化を打ち消す方向に移動)により、
元の電解質の溶解度や電離度が小さくなる。
これを共通イオン効果という。
沈殿を多く得たいときに利用できる。
例:
NaCl(固) ⇄ Na⁺ + Cl⁻
NaCl飽和水溶液に NaCl(固) や NaNO₃(Na⁺を与える塩)または HCl を加えると、
平衡が左に移動し NaCl結晶が析出する。
例題1
0.020 mol/L の CaCl₂水溶液 60 mL に
0.080 mol/L の NaF水溶液 40 mL を加えたとき、CaF₂の沈殿は生じるか。
Ksp(CaF₂) = [Ca²⁺][F⁻]² = 3.9×10⁻¹¹ (mol/L)³
混合後の濃度:
[Ca²⁺] = 0.012 mol/L
[F⁻] = 0.032 mol/L
Qsp = [Ca²⁺][F⁻]² = 1.23×10⁻⁵ (mol/L)³
Qsp = 1.23×10⁻⁵ > Ksp = 3.9×10⁻¹¹ より、CaF₂の沈殿が生じる。
例題2:PbCl₂の溶解度
Ksp = [Pb²⁺][Cl⁻]² = 3.2×10⁻⁸ (mol/L)³
(1) 水に対する PbCl₂ の溶解度
PbCl₂(固) ⇄ Pb²⁺ + 2Cl⁻
Ksp = 4x³ = 3.2×10⁻⁸ → x = 2.0×10⁻³ mol/L
(2) 0.10 mol/L HCl中での溶解度
PbCl₂(固) ⇄ Pb²⁺ + 2Cl⁻
HCl → H⁺ + Cl⁻(濃度 0.10 mol/L)
溶解度を y mol/L とすると、
[Pb²⁺] = y, [Cl⁻] = 0.10 + 2y ≈ 0.10
Ksp = y × 0.10² = 3.2×10⁻⁸ → y = 3.2×10⁻⁶ mol/L
補足解説
(1) 溶解度とは「溶媒1Lに溶ける最大の溶質の物質量[mol]」である。
限界まで溶質が溶けた飽和溶液では溶解平衡が成立している。
Ksp = [Pb²⁺][Cl⁻]² を利用して溶解度を求めることができる。
(2) 平衡に共通イオン(Cl⁻)を与える物質 HCl を加えると、
Cl⁻濃度が増して平衡は左に移動し、PbCl₂の溶解度は小さくなる(共通イオン効果)。
[Cl⁻] は HCl 由来と PbCl₂ 由来の和だが、後者は非常に小さい。
したがって 0.10 + 2y ≈ 0.10 と近似できる。
y は 0.10 に対して極めて小さい(0.10 ≫ 2y)ため、この近似は有効数字2桁に影響しない。
実際、0.10 + 2y = 0.1000064 なので近似は妥当。