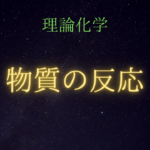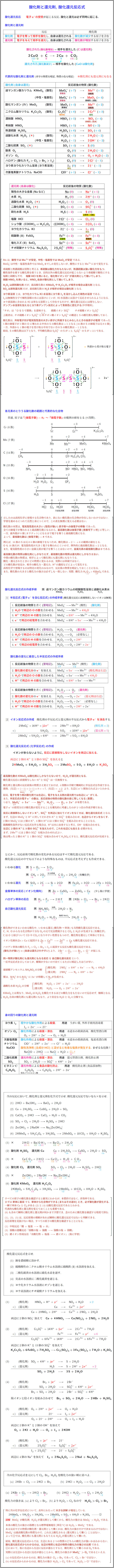
酸化還元反応 電子e⁻の授受が起こる反応. 酸化と還元は必ず同時に起こる.
酸化剤と還元剤
酸化剤 電子を奪って相手を酸化し, 自身は還元される. 酸化数が減少する原子を含む.
還元剤 電子を与えて相手を還元し, 自身は酸化される. 酸化数が増加する原子を含む.
代表的な酸化剤と還元剤(赤字の物質を暗記, 物質の色も暗記)*酸化剤にも還元剤にもなる
酸化剤(自身は還元)
反応前後の物質(酸化数)
過マンガン酸カリウム KMnO₄(酸性) MnO₄⁻(+7)→ Mn²⁺(+2)
(中性・塩基性) MnO₄⁻(+7)→ MnO₂(+4)
酸化マンガン(Ⅳ) MnO₂(酸性) MnO₂(+4)→ Mn²⁺(+2)
二クロム酸カリウム K₂Cr₂O₇(酸性) Cr₂O₇²⁻(+6)→ 2Cr³⁺(+3)
濃硝酸 HNO₃ HNO₃(+5)→ NO₂(+4)
希硝酸 HNO₃ HNO₃(+5)→ NO(+2)
熱濃硫酸 H₂SO₄ H₂SO₄(+6)→ SO₂(+4)
過酸化水素 H₂O₂(*)(酸性) H₂O₂(−1)→ 2H₂O(−2)
(中性・塩基性) H₂O₂(−1)→ 2OH⁻(−2)
二酸化硫黄 SO₂(*) SO₂(+4)→ S(0)
酸素 O₂ O₂(0)→ 2H₂O(−2)
オゾン O₃ O₃(0)→ O₂ + H₂O(−2)
ハロゲン(酸化力 F₂ > Cl₂ > Br₂ > I₂) Cl₂(0)→ 2Cl⁻(−1)
ヨウ素ヨウ化カリウム溶液(ヨウ素溶液) I₂(0)→ 2I⁻(−1)
次亜塩素酸ナトリウム NaClO ClO⁻(+1)→ Cl⁻(−1)
還元剤(自身は酸化)
反応前後の物質(酸化数)
陽性の大きな金属(Naなど) Na(0)→ Na⁺(+1)
水素 H₂ H₂(0)→ 2H⁺(+1)
過酸化水素 H₂O₂(*) H₂O₂(−1)→ O₂(0)
二酸化硫黄 SO₂(*) SO₂(+4)→ SO₄²⁻(+6)
硫化水素 H₂S H₂S(−2)→ S(0)
塩酸 HCl 2Cl⁻(−1)→ Cl₂(0)
シュウ酸 (COOH)₂ または H₂C₂O₄ (COOH)₂(+3)→ 2CO₂(+4)
ヨウ化カリウム KI 2I⁻(−1)→ I₂(0)
硫酸鉄(Ⅱ) FeSO₄ Fe²⁺(+2)→ Fe³⁺(+3)
塩化スズ(Ⅱ) SnCl₂ Sn²⁺(+2)→ Sn⁴⁺(+4)
チオ硫酸ナトリウム Na₂S₂O₃ S₂O₃²⁻(特殊)→ S₄O₆²⁻(特殊)
Mnは, 酸性ではMn²⁺が安定, 中性・塩基性ではMnO₂が安定である.
MnO₄⁻は中性・塩基性条件ではMnO₂までしか変化しないが, 酸性にするとMn²⁺にまで変化する.
希硫酸と熱濃硫酸は別物と考える. 希硫酸は酸化力をもたないが, 熱濃硫酸は強い酸化力をもつ.
酸性条件を要する酸化剤を使うとき, 目的以外の酸化還元反応が起こらないよう希硫酸で酸性にする.
塩酸と硝酸も不可. 塩酸HClを用いると, 塩化物イオンCl⁻が還元剤として働いてしまう.
硝酸HNO₃を用いると, HNO₃自身が酸化剤として働いてしまう.
H₂O₂は原則酸化剤だが, 最高酸化数のKMnO₄やK₂Cr₂O₇が相手の場合は還元剤となる.
SO₂は原則還元剤だが, 最低酸化数のH₂Sが相手の場合は酸化剤となる.
ヨウ素溶液とは, ヨウ化カリウムKI水溶液にヨウ素I₂を溶かし込んだ褐色の溶液である.
I₂は無極性分子で極性溶媒の水には溶けにくいが, KI水溶液には溶けて反応させられるようになる.
ヨウ素溶液に含まれるKIは単なる溶質として存在するだけで, 酸化還元反応には関与しない.
デンプン水溶液を加えるとヨウ素デンプン反応によって青紫色に変化する(中学理科).
「チオ」は「OをSで置換」を意味する. 硫酸イオン SO₄²⁻, チオ硫酸イオン S₂O₃²⁻.
上級者は, チオ硫酸イオン S₂O₃²⁻ と四チオン酸イオン S₄O₆²⁻ の構造とSの酸化数も理解しておく.
酸化数は, 共有電子対が電気陰性度の大きい原子に所属するとみなしたときの各原子の電荷であった.
5個の価電子が3個のOに奪われる中央のSの酸化数は+5となる(16族のSの価電子は元々6個).
一方, 外部から1個の電子を受け取る中央でない方のSの酸化数は−1となる.
結局, Sの酸化数は以下となり, 平均酸化数はS₂O₃²⁻のSが+2, S₄O₆²⁻のSが+2.5である.
チオ硫酸イオンは四面体構造をとる. 中心のS原子の酸化数は変化しないが, 頂点のS原子の酸化数は変化し, 2個のチオ硫酸イオンのS原子どうしがジスルフィド結合 −S−S− を形成し, 1個の四チオン酸イオンになる.
各元素のとりうる酸化数の範囲と代表的な化合物
普通, 原子は「(価電子数)−8」~「価電子数」の範囲の値をとる(8段階).
Cr(6族)
0: Cr
+3: Cr³⁺
+6: K₂Cr₂O₇
Mn(7族)
0: Mn
+2: Mn²⁺
+4: MnO₂
+7: KMnO₄
C(14族)
−4: CH₄
0: C
+2: CO
+3: H₂C₂O₄
+4: CO₂
N(15族)
−3: NH₃
0: N₂
+2: NO
+3: HNO₂
+4: NO₂
+5: HNO₃
O(16族)
−2: H₂O
−1: H₂O₂
0: O₂
+2: OF₂
S(16族)
−2: H₂S
0: S
+4: SO₂
+6: H₂SO₄
Cl(17族)
−1: HCl
0: Cl₂
+1: HClO
+3: HClO₂
+5: HClO₃
+7: HClO₄
示したのは高校化学に登場する化合物であり, 表にない酸化数の化合物が存在しないわけではない.
学習を進めるにつれて自然と身につくので, この表を無理に覚える必要はない.
酸化数の本質は, 電気陰性度の大きい(陰性が強い)原子側への価電子の移動であった.
全ての価電子が奪われると最高酸化数になるから, 最高酸化数は価電子数(族番号下1桁)に等しい.
一方, 最外殻が8個(オクテット)になるまで電子を奪うと最低酸化数になる.
よって, 最低酸化数は(価電子数)−8である.
例えば, 16族のSは元々6個の価電子をもつため, 酸化数は−2 ~ +6の範囲の値をとる.
Oも16族だが, 電気陰性度が大きく電子を奪われにくいので, 例外的に最高酸化数は+2となる.
また, 電気陰性度の小さい金属元素が電子を奪うことはないので, 金属元素の最低酸化数は0である.
最高酸化数の物質は酸化剤にしかなりえず, 最低酸化数の物質は還元剤にしかなりえない.
中間の酸化数の物質は, 相手によって酸化剤にも還元剤にもなりうる.
酸化・還元されたときにどの物質に変わるかは, 実際には単純ではなく, どの酸化数が安定か, 相手の酸化力・還元力, H⁺の濃度などによって変化する.
高校化学で登場するのは特定の変化のみなので, 反応後の物質を暗記しておくことになる.
また, 酸化数の大きさと酸化力の強さは必ずしも一致しない. 実際, 酸化力 H₂O₂(−1) > KMnO₄(+7) である.
酸化還元反応式の作成手順 例 過マンガン酸カリウムの硫酸酸性溶液と過酸化水素水
[1] 半反応式(電子e⁻を含む反応式)の作成手順(酸化還元反応に直接関係しないイオンは無視)
反応前後の物質を書く(要暗記). MnO₄⁻ → Mn²⁺ (酸性) (酸化剤)
H₂Oで両辺のOの数を合わせる. MnO₄⁻ → Mn²⁺ + 4H₂O
H⁺で両辺のHの数を合わせる. MnO₄⁻ + 8H⁺ → Mn²⁺ + 4H₂O
e⁻で両辺の総電荷を合わせる. MnO₄⁻ + 8H⁺ + 5e⁻ → Mn²⁺ + 4H₂O
反応前後の物質を書く(要暗記). H₂O₂ → O₂ (還元剤)
H₂Oで両辺のOの数を合わせる. H₂O₂ → O₂ (必要なし)
H⁺で両辺のHの数を合わせる. H₂O₂ → O₂ + 2H⁺
e⁻で両辺の総電荷を合わせる. H₂O₂ → O₂ + 2H⁺ + 2e⁻
酸化数の変化に着目した半反応式の作成手順
反応前後の物質を書く(要暗記). Mn⁺⁷O₄⁻ → Mn⁺² (酸性) (酸化剤)
酸化数の変化分のe⁻を加える. MnO₄⁻ + 5e⁻ → Mn²⁺ (酸化剤は左辺)
H₂Oで両辺のOの数を合わせる. MnO₄⁻ + 5e⁻ → Mn²⁺ + 4H₂O
H⁺で両辺のHの数を合わせる. MnO₄⁻ + 8H⁺ + 5e⁻ → Mn²⁺
反応前後の物質を書く(要暗記). H₂O⁻¹₂ → O⁰₂ (還元剤)
酸化数の変化分のe⁻を加える. H₂O₂ → O₂ + 2e⁻ (還元剤は右辺)
H₂Oで両辺のOの数を合わせる. H₂O₂ → O₂ + 2e⁻ (必要なし)
H⁺で両辺のHの数を合わせる. H₂O₂ → O₂ + 2H⁺ + 2e⁻
[2] イオン反応式の作成 酸化剤の半反応式と還元剤の半反応式から電子e⁻を消去する.
2MnO₄⁻ + 16H⁺ + 10e⁻ → 2Mn²⁺ + 8H₂O (酸化剤×2)
5H₂O₂ → 5O₂ + 10H⁺ + 10e⁻ (還元剤×5)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
2MnO₄⁻ + 5H₂O₂ + 6H⁺ → 2Mn²⁺ + 5O₂ + 8H₂O
[3] 酸化還元反応式(化学反応式)の作成
イオンが余らないように, 反応に直接関与しないイオンを両辺に加える.
両辺に2個のK⁺と3個のSO₄²⁻を加えると
2KMnO₄ + 5H₂O₂ + 3H₂SO₄ → 2MnSO₄ + 5O₂ + 8H₂O + K₂SO₄
[補足説明]
最高酸化数のKMnO₄は酸化剤にしかなりえないので, H₂O₂が還元剤となる.
酸化還元反応に直接関与しないK⁺とSO₄²⁻は一旦無視する.
酸化剤と還元剤の反応前後の物質さえ覚えておけば, 4段階の手順で機械的に半反応式を作成できる.
最後, (左辺)=MnO₄⁻(-1)+H⁺(+1)×8=+7, (右辺)=Mn²⁺(+2)より, 左辺にe⁻5個加えればよいとわかる.
結局, 電子を奪う側の酸化剤では左辺に, 電子を与える側の還元剤では右辺にe⁻がくる.
また, 半反応式の電子e⁻の数は, 反応前後の物質の酸化数の差に等しくなる(重要).
つまり, Mn⁺⁷O₄⁻ + 5e⁻ → Mn⁺², H₂O⁻¹₂ → O⁰₂ + 2e⁻ が本質である.
電子e⁻の授受分だけ酸化数が変化することを優先的に考慮したのが2つ目の作成手順である.
反応に直接関与しないイオンK⁺, SO₄²⁻を両辺に加えてイオンをなくせば, 酸化還元反応式となる.
まず, 左辺のMnO₄⁻とH⁺に対してそれぞれK⁺とSO₄²⁻を組み合わせ, 左辺からイオンをなくす.
2個のMnO₄⁻には2個のK⁺, 6個のH⁺には3個のSO₄²⁻を組み合わせることになる.
硫酸酸性条件がない反応式を作る場合は, H⁺は水に由来すると考え, OH⁻を組み合わせる.
左辺に2個のK⁺と3個のSO₄²⁻を加えたので, これを右辺にも加える必要がある.
まず, 2Mn²⁺には2個のSO₄²⁻を組み合わせればよい.
後は残った2個のK⁺と1個のSO₄²⁻を組み合わせてK₂SO₄にすると, 酸化還元反応式が完成する.
とにかく, 反応前後で酸化数の変化がある反応はすべて酸化還元反応である.
酸化還元反応の中でも以下のような特殊なものは, 半反応式を考えずとも作成できる.
酸化 例 S⁰ + O⁰₂ → S⁺⁴O⁻²₂
例 C⁻⁴H₄ + 2O⁰₂ → C⁺⁴O⁻²₂ + 2H₂O⁻² (有機化学)
還元 例 Si⁺⁴O₂ + 2C⁰ → Si⁰ + 2C⁺²O
例 Fe⁺³₂O₃ + 3C⁺²O → 2Fe⁰ + 3C⁺⁴O₂
金属単体の反応(イオン化傾向) 例 Zn⁰ + Cu⁺²SO₄ → Zn⁺²SO₄ + Cu⁰ (少し後に学習)
ハロゲン単体の反応 例 H⁰₂ + F⁰₂ → 2H⁺¹F⁻¹
例 2KBr⁻¹ + Cl⁰₂ → Br⁰₂ + 2KCl⁻¹
自己酸化還元反応 例 N⁻³H₄ + N⁺³O₂ → 2H₂O + N⁰₂
例 H₂O⁻¹₂ + H₂O⁻¹₂ →[触媒MnO₂] 2H₂O⁻² + O⁰₂
酸化物ができるいわゆる酸化や, いわゆる還元(酸化物→単体)も当然酸化還元反応である.
C, H, Oからなる化合物が十分なO₂の元で完全燃焼するとCO₂とH₂Oが生成する(有機化学).
CはOと結びついてCOやCO₂になりやすい性質をもつので, 酸化物を還元して単体にできる.
イオン化傾向 Zn>Cu に起因する Zn⁰ + Cu²⁺ → Zn²⁺ + Cu⁰ も酸化還元反応である.
ハロゲン単体の酸化力 F₂>Cl₂>Br₂>I₂ に起因する反応も酸化還元反応である.
(酸化力が強い)=(自身は還元されやすい)より, 2Br⁻ + Cl₂ → Br₂ + 2Cl⁻ が起こる.
同一物質が酸化剤にも還元剤にもなる反応を自己酸化還元反応という.
一応半反応式を示しておくが, 種類が少ないので出てくるたびに暗記したほうが早い.
亜硝酸アンモニウム NH₄NO₂ の分解
(酸化剤) 2NO₂⁻ + 8H⁺ + 6e⁻ → N₂ + 4H₂O
(還元剤) 2NH₄⁺ → N₂ + 8H⁺ + 6e⁻
要は, N⁻³H₄⁺ から N⁺³O₂⁻ に 3e⁻ が移動して N⁰₂ が生成する.
過酸化水素 H₂O₂ の分解
(酸化剤) H₂O₂ + 2H⁺ + 2e⁻ → 2H₂O
(還元剤) H₂O₂ → O₂ + 2H⁺ + 2e⁻
KMnO₄ とは異なり, MnO₂ は H₂O₂ を酸化できるほどの酸化力をもたないので反応せず, 触媒となる.
H₂O₂ 自身が酸化剤にも還元剤にもなり, より安定な H₂O と O₂ に分解する.
身の回りの酸化剤と還元剤
物質 主な作用・用途
ヨウ素 I₂ 穏やかな酸化作用による殺菌. 用途:うがい薬, 外科手術用消毒薬
I₂ + 2e⁻ → 2I⁻
オゾン O₃ 酸化作用による殺菌・漂白. 用途:水道水の殺菌消毒, 酸化型漂白剤
O₃ + 2H⁺ + 2e⁻ → O₂ + H₂O
次亜塩素酸 NaClO 酸化作用による殺菌・漂白. 用途:水道水の殺菌消毒, 塩素系漂白剤
ClO⁻ + 2H⁺ + 2e⁻ → Cl⁻ + H₂O
NaClO + 2HCl → NaCl + H₂O + Cl₂
(酸性洗浄剤HClと混ぜると有毒な塩素が発生する. まぜるな危険!)
二酸化硫黄 SO₂ 還元作用による殺菌・漂白. 用途:還元型漂白剤, 酸化防止剤
SO₂ + 2H₂O → SO₄²⁻ + 4H⁺ + 2e⁻
ビタミンC C₆H₈O₆ 還元作用による食品の酸化防止. 用途:酸化防止剤(食品添加物)
C₆H₈O₆ → C₆H₆O₆ + 2H⁺ + 2e⁻ (別名:アスコルビン酸)
次の反応において, 酸化剤と還元剤を化学式で示せ. 酸化還元反応でないなら×を示せ.
(1) 2HCl + Ba(OH)₂ → BaCl₂ + 2H₂O
(2) Cu + 2H₂SO₄ → CuSO₄ + 2H₂O + SO₂
(3) CaCO₃ + 2HCl → CaCl₂ + H₂O + CO₂
(4) SO₂ + Cl₂ + 2H₂O → H₂SO₄ + 2HCl
(5) Zn(OH)₂ + 2NaOH → Na₂[Zn(OH)₄]
(6) 2KMnO₄ + 5H₂C₂O₄ + 3H₂SO₄ → 2MnSO₄ + 10CO₂ + 8H₂O + K₂SO₄
(1) ×
(2) 酸化剤:H₂SO₄ 還元剤:Cu
Cu⁰ + 2H₂S⁺⁶O₄ → Cu²⁺SO₄ + 2H₂O + S⁺⁴O₂
(3) ×
Ca²⁺C⁺⁴O₃ + 2H⁺Cl⁻ → Ca²⁺Cl₂ + H₂O + C⁺⁴O₂
(4) 酸化剤:Cl₂ 還元剤:SO₂
S⁺⁴O₂ + Cl⁰₂ + 2H₂O → H₂S⁺⁶O₄ + 2HCl⁻¹
(5) ×
Zn²⁺(OH⁻)₂ + 2Na⁺OH⁻ → Na₂[Zn²⁺(OH⁻)₄]
(6) 酸化剤:KMnO₄ 還元剤:H₂C₂O₄
2KMn⁺⁷O₄ + 5H₂C⁺³₂O₄ + 3H₂SO₄ → 2Mn⁺²SO₄ + 10C⁺⁴O₂ + 8H₂O + K₂SO₄
すべての原子の酸化数を確認すると確実にわかるが, 本質的ではなく, 非効率である.
まずは単体に着目する. 単体から化合物ができる(またはその逆の)とき, 必ず酸化数が変化する.
一瞬で単体CuとCl₂がある(2)と(4)は酸化還元反応であるとわかる.
代表的な酸化剤と還元剤を覚えておくことも重要である.
(6)も含めて瞬時に酸化剤と還元剤が何かまで予想でき, 念のために酸化数を確認する程度で済む.
(1),(3),(5)は, 反応原理の理解があれば瞬時に酸化還元反応ではないと判断できる.
反応原理を見抜けない場合, すべての原子の酸化数を確認することになる.
(1) 中和反応「酸 + 塩基 → 塩 + 水」
(3) 弱酸の遊離反応「弱酸の塩 + 強酸 → 強酸の塩 + 弱酸」
(5) 錯イオン形成反応「水酸化物 + 塩基 → 錯イオン」(後に学習)
酸化還元反応式を示せ.
(1) 銅を濃硝酸に溶かす.
酸化剤:HNO₃ + H⁺ + e⁻ → NO₂ + H₂O ×2
還元剤:Cu → Cu²⁺ + 2e⁻
Cu + 4HNO₃ → Cu(NO₃)₂ + 2NO₂ + 2H₂O
(2) 硫酸酸性の二クロム酸カリウム水溶液に硫酸鉄(II)水溶液を加える.
Cr₂O₇²⁻ + 14H⁺ + 6e⁻ → 2Cr³⁺ + 7H₂O
Fe²⁺ → Fe³⁺ + e⁻ ×6
Cr₂O₇²⁻ + 6Fe²⁺ + 14H⁺ → 2Cr³⁺ + 6Fe³⁺ + 7H₂O
両辺に2K⁺と13SO₄²⁻を加えて
K₂Cr₂O₇ + 6FeSO₄ + 7H₂SO₄ → Cr₂(SO₄)₃ + 3Fe₂(SO₄)₃ + 7H₂O + K₂SO₄
(3) SO₂ + 2H₂S → 3S + 2H₂O
(4) Br₂ + SO₂ + 2H₂O → 2Br⁻ + SO₄²⁻ + 4H⁺
陽イオンと陰イオンを組み合わせて
Br₂ + SO₂ + 2H₂O → 2HBr + H₂SO₄
(5) O₃ + 2H⁺ + 2e⁻ → O₂ + H₂O
2I⁻ → I₂ + 2e⁻
O₃ + 2I⁻ + 2H⁺ → O₂ + I₂ + H₂O
両辺に2K⁺と2OH⁻を加えて
O₃ + 2KI + H₂O → O₂ + I₂ + 2KOH
(6) I₂ + 2S₂O₃²⁻ → 2I⁻ + S₄O₆²⁻
両辺に4Na⁺を加えて
I₂ + 2Na₂S₂O₃ → 2NaI + Na₂S₄O₆
次の化学反応式を元にして Cl₂, Br₂, H₂O₂ を酸化力の強い順に並べよ.
(a) 2KBr + Cl₂ → 2KCl + Br₂
(b) 2HCl + H₂O₂ → Cl₂ + 2H₂O
(a)より Cl₂ > Br₂, (b)より H₂O₂ > Cl₂ なので
H₂O₂ > Cl₂ > Br₂
特に次の化学反応式について, 長年にわたって大きな誤解が蔓延している.
2KMn⁺⁷O₄ + 5H₂O⁻¹₂ + 3H₂SO₄ → 2Mn⁺²SO₄ + 5O⁰₂ + 8H₂O + K₂SO₄ …①
誤解:MnO₄⁻ が酸化剤, H₂O₂ が還元剤として働くから, 酸化力の強さは MnO₄⁻ > H₂O₂ である.
本来の酸化力の強さの指標となる標準電極電位[単位V]は H₂O₂ > MnO₄⁻ である.
ある反応でどの物質が酸化剤・還元剤として働くかは, 酸化力の強さだけで決まるわけではない.
MnO₄⁻ は最高酸化数の物質なので, これ以上酸化される(還元剤として働く)ことはない.
よって①では, 酸化剤にも還元剤にもなりえるH₂O₂が還元剤として働いた.
結局, 酸化還元反応式からでは, 左辺にある2つの物質のどちらの酸化力が強いかはわからない.
酸化還元反応式からわかるのは, 左辺の物質と右辺の物質の酸化力の強さの比較である.
①において, 仮に右辺から左辺に反応が進むとすると, 酸化剤として働くのはO₂である.
実際には左辺から右辺に反応が進むことから, 酸化力の強さが MnO₄⁻ > O₂ であるといえる.
(a)の反応式からわかるのは, 酸化力の強さ Cl₂ > Br₂ であって, Cl₂ > Br⁻ ではない.
(b)の反応式からわかるのは, 酸化力の強さ H₂O₂ > Cl₂ であって, H₂O₂ > Cl⁻ ではない.