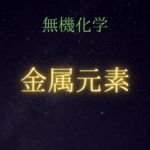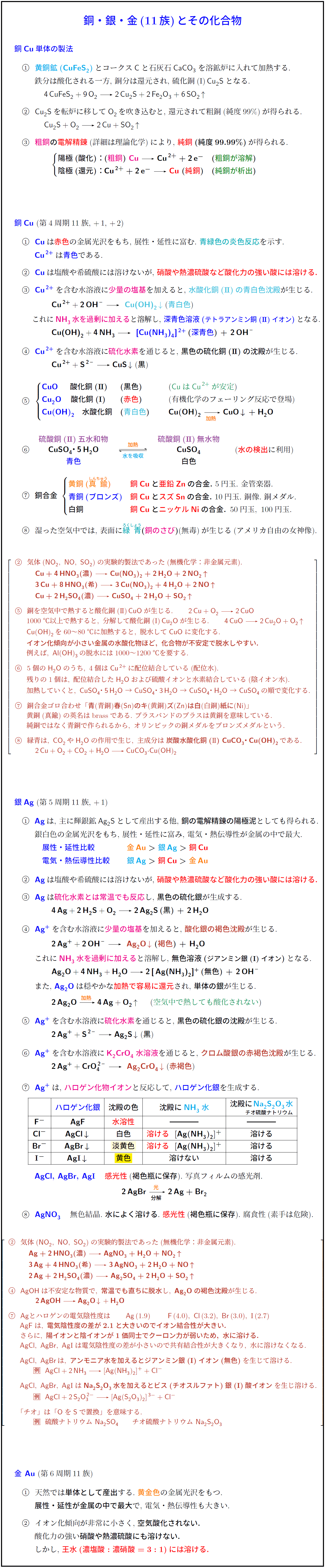
銅・銀・金(11族)とその化合物
銅Cu単体の製法
① 黄銅鉱(CuFeS₂)とコークスCと石灰石CaCO₃を溶鉱炉に入れて加熱する。
鉄分は酸化される一方、銅分は還元され、硫化銅(I)Cu₂Sとなる。
4CuFeS₂ + 9O₂ → 2Cu₂S + 2Fe₂O₃ + 6SO₂↑
② Cu₂Sを転炉に移してO₂を吹き込むと、還元されて粗銅(純度99%)が得られる。
Cu₂S + O₂ → 2Cu + SO₂↑
③ 粗銅の電解精錬(詳細は理論化学)により、純銅(純度99.99%)が得られる。
陽極(酸化):Cu → Cu²⁺ + 2e⁻ (粗銅が溶解)
陰極(還元):Cu²⁺ + 2e⁻ → Cu (純銅が析出)
銅Cu(第4周期11族, +1, +2)
① Cuは赤色の金属光沢をもち、展性・延性に富む。青緑色の炎色反応を示す。
Cu²⁺は青色である。
② Cuは塩酸や希硫酸には溶けないが、硝酸や熱濃硫酸など酸化力の強い酸には溶ける。
③ Cu²⁺を含む水溶液に少量の塩基を加えると、水酸化銅(Ⅱ)の青白色沈殿が生じる。
Cu²⁺ + 2OH⁻ → Cu(OH)₂↓(青白色)
これにNH₃水を過剰に加えると溶解し、深青色溶液(テトラアンミン銅(Ⅱ)イオン)となる。
Cu(OH)₂ + 4NH₃ → [Cu(NH₃)₄]²⁺(深青色) + 2OH⁻
④ Cu²⁺を含む水溶液に硫化水素を通じると、黒色の硫化銅(Ⅱ)の沈殿が生じる。
Cu²⁺ + S²⁻ → CuS↓(黒)
⑤ CuO(黒色):酸化銅(Ⅱ)
Cu₂O(赤色):酸化銅(I)(フェーリング反応で登場)
Cu(OH)₂(青白色):加熱によりCuOとH₂Oに分解
⑥ 硫酸銅(Ⅱ)五水和物 CuSO₄・5H₂O ⇄ CuSO₄(青⇄白)
水の検出に利用される。
⑦ 銅合金
・黄銅(真鍮):Cu + Zn(5円玉、金管楽器)
・青銅(ブロンズ):Cu + Sn(10円玉、銅像、銅メダル)
・白銅:Cu + Ni(50円玉、100円玉)
⑧ 湿った空気中では表面に緑青(CuCO₃・Cu(OH)₂, 無毒)が生じる(自由の女神像)。
🔹第2部(銀の性質〜ハロゲン化銀まで)
銀Ag(第5周期11族, +1)
① Agは主に輝銀鉱Ag₂Sとして産出するほか、銅の電解精錬の陽極泥としても得られる。
銀白色の金属光沢をもち、展性・延性に富み、電気・熱伝導性が最大。
展性・延性比較:Au > Ag > Cu
電気・熱伝導性比較:Ag > Cu > Au
② Agは塩酸や希硫酸には溶けないが、硝酸や熱濃硫酸など酸化力の強い酸には溶ける。
③ Agは硫化水素と常温でも反応し、黒色の硫化銀が生成する。
4Ag + 2H₂S + O₂ → 2Ag₂S(黒) + 2H₂O
④ Ag⁺を含む水溶液に少量の塩基を加えると、酸化銀の褐色沈殿が生じる。
2Ag⁺ + 2OH⁻ → Ag₂O↓(褐色) + H₂O
これにNH₃水を過剰に加えると溶解し、無色溶液(ジアンミン銀(I)イオン)となる。
Ag₂O + 4NH₃ + H₂O → 2[Ag(NH₃)₂]⁺ + 2OH⁻
Ag₂Oは加熱により容易に還元され、銀が生じる。
2Ag₂O → 4Ag + O₂↑
⑤ Ag⁺を含む水溶液に硫化水素を通じると、黒色の硫化銀の沈殿が生じる。
2Ag⁺ + S²⁻ → Ag₂S↓
⑥ Ag⁺を含む水溶液にK₂CrO₄を加えると、クロム酸銀Ag₂CrO₄(赤褐色沈殿)が生じる。
2Ag⁺ + CrO₄²⁻ → Ag₂CrO₄↓(赤褐色)
⑦ Ag⁺はハロゲン化物イオンと反応し、ハロゲン化銀を生成する。
ハロゲン化銀 沈殿の色 NH₃水への溶解性 Na₂S₂O₃水への溶解性
AgF 水溶性 — —
AgCl↓ 白色 溶ける([Ag(NH₃)₂]⁺) 溶ける
AgBr↓ 淡黄色 溶ける([Ag(NH₃)₂]⁺) 溶ける
AgI↓ 黄色 溶けない 溶ける
AgCl, AgBr, AgI は感光性をもち褐色瓶で保存。写真フィルムの感光剤。
2AgBr → 2Ag + Br₂(光による分解)
⑧ AgNO₃:無色結晶、水に可溶、感光性あり(褐色瓶で保存)、腐食性。
🔹第3部(金と全体補注)
金Au(第6周期11族)
① 天然で単体として産出する。黄金色の金属光沢をもち、展性・延性が最大。
② イオン化傾向が非常に小さく、空気酸化されず、硝酸や熱濃硫酸にも溶けない。
しかし王水(濃塩酸:濃硝酸=3:1)には溶ける。