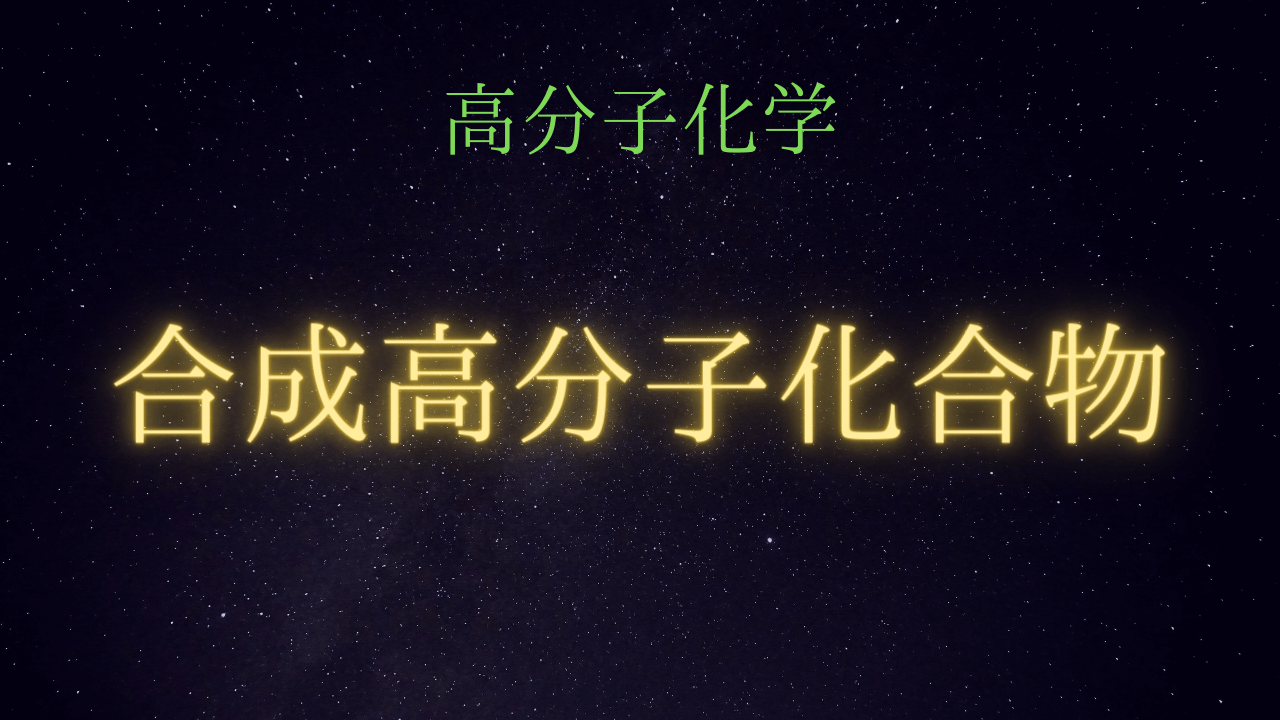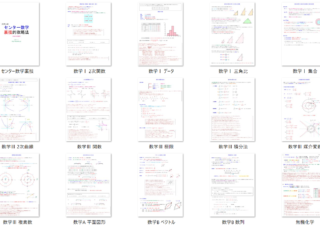合成高分子化合物の概要
高分子化学の本格的な発展は20世紀に始まった。1907年、熱に強く電気を通さないベークライト(フェノール樹脂)が誕生し、電気製品や工業材料に広く使われるようになった。これが近代的なプラスチック工業の出発点である。
1930年代にはアメリカでナイロンが発明され、軽くて丈夫な人工繊維として一気に普及した。特にナイロン66は強度・耐熱性に優れ、衣服やロープ、軍需品、自動車部品など幅広く利用された。高校化学でも代表的な合成繊維として必ず登場する、象徴的な高分子素材である。
1940年代にはポリエチレンテレフタラート(PET)が開発され、フィルムや繊維として利用が始まった。1960年代にPETボトルとして実用化されると急速に普及し、現在は衣類(ポリエステル)・飲料容器・包装材など生活に欠かせない素材となっている。高校化学ではナイロンと並ぶ重要な合成高分子である。
同時期に、ポリエチレン(PE)やポリ塩化ビニル(PVC)など基本的なプラスチックが次々と実用化された。軽量で加工しやすく、水や薬品に強いことから、容器・包装・配管・電線の被覆など用途は多岐にわたる。分子のつながり方・含まれる原子や官能基の違いが、透明性・柔軟性・耐熱性・難燃性などの性質を決定している。
戦後には合成ゴム(SBR・NBRなど)が急速に普及し、自動車タイヤの大量生産を支えた。ブタジエンやスチレンなど異なる成分を組み合わせることで、弾性や耐油性を自在に調整できることが特徴である。
さらに、日本独自の発展としてビニロンがある。ポリビニルアルコール(PVA)を原料とするこの繊維は、丈夫で吸水性が高く、作業服・漁網・ロープなどに広く用いられた。国産技術として世界的に評価され、日本の合成繊維産業の基盤を築いた重要な素材である。
このように、合成繊維・プラスチック・合成ゴムといった高分子素材の発見と改良は、日常生活の変化と密接に結びついている。高校化学で扱う「重合反応」「構造の違い」「性質の理解」は、それらの素材がどのように作られ、どのように利用されているかを理解するための基礎となる。
合成高分子化合物の攻略
高分子化合物分野は高校化学の終盤で扱われるため、学習時間が不足しがちである。また、構造式の複雑さや高分子特有の計算問題に抵抗を感じる学生も多く、手薄になりやすい分野である。
しかし、大学受験では出題頻度が高く、暗記量も多いため、しっかりと学習したかどうかが合否に大きく影響しうる。理論・無機・有機の陰に隠れがちだが、決して軽視できない分野である。
合成高分子の理解には、有機化学の基礎力が不可欠である。天然高分子化合物と同様に構造式を自分で描く過程で理解が深まるため、自分の手で構造式を描きながら学習することが重要重要となる。
当カテゴリでは、基本事項から頻出問題、さらに難関大レベルの発展内容まで体系的に整理している。確実な得点源として活用してほしい。