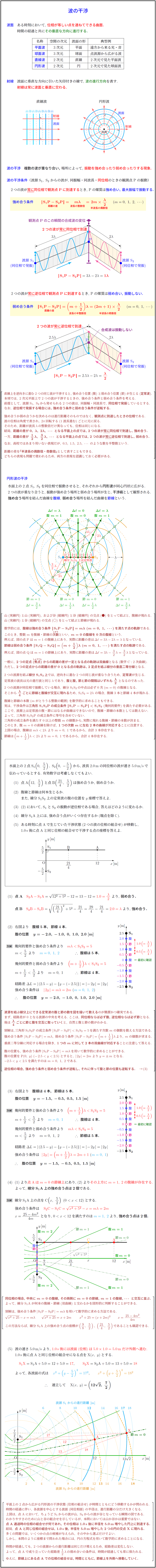
強め合う条件と弱め合う条件のGeoGebraアニメーション
円形波の干渉のGeogebraアニメーション
波の干渉
波面 ある時刻において, 位相が等しい点を連ねてできる曲面.
時間の経過と共にその垂直な方向に進行する.
名称 & 空間の次元 & 波面の形 & 典型例
平面波 & 3次元 & 平面 & 遠方から来る光・音
球面波 & 3次元 & 球面 & 点波源から広がる波
直線波 & 2次元 & 直線 & 2次元で見た平面波
円形波 & 2次元 & 円 & 2次元で見た球面波
射線 波面に垂直な方向に引いた矢印付きの線で, 波の進行方向を表す.
射線は常に波面と垂直に交わる.
波の干渉 複数の波が重なり合い, 場所によって, 振動を強め合ったり弱め合ったりする現象.
波の干渉条件(波源S1, S2からの波が, 同振幅・同波長・同位相のときの観測点Pの振動) つの波が常に同位相で観測点Pに到達するとき, Pの媒質は強め合い, 最大振幅で振動する.
強め合う条件 距離の差S1P-S2P=波長の整数倍mλ=半波長の偶数倍2m×λ/2 (m=0, 1, 2, …)
2つの波が常に逆位相で観測点Pに到達するとき, Pの媒質は弱め合い, 振動しない.
弱め合う条件 距離の差S1P-S2P=波長の半整数倍(m+1/2)λ=半波長の奇数倍(1/2)(2m+1)×λ/2 (m=0, 1, …)
直線上を逆向きに進む2つの同じ波が干渉すると, 強め合う位置(腹)と弱め合う位置(節)が生じる(定常波).
本項では, 2次元平面上で2つの波が干渉するときの, 強め合う条件と弱め合う条件を考える.
前提として, 波源S1, S2から発せられる2つの波は, 同振幅・同波長で, 同位相で発振しているとする.
なお, 逆位相で発振する場合には, 強め合う条件と弱め合う条件が逆転する.
強め合うか弱め合うかを決めるのは進行距離そのものではなく, 観測点に到達したときの位相である.
波の位相は角度で表され, 2π回転する(1波長進む)ごとに元に戻る.
そのため, 距離が波長λの整数倍だけ異なっても, 位相は同じになる.
結局, 距離の差が0, λ, 2λ, … となる平面上の点では, 2つの波が常に同位相で到達し, 強め合う.
一方, 距離の差が 1/2λ, 3/2λ, … となる平面上の点では, 2つの波が常に逆位相で到達し, 弱め合う.
なお, 高校ではあまり用いない表現だが, 0.5, 1.5, 2.5, … のような数を半整数という.
距離の差を「半波長の偶数倍・奇数倍」として表すこともできる.
どちらの表現も問題で使われるため, 両方の表現を認識しておく必要がある.
円形波の干渉
水面上の2点S1, S2を同位相で振動させると, それぞれから円形波が同心円状に広がる. つの波が重なり合うと, 振動が強め合う場所と弱め合う場所が生じ, 干渉縞として観察される.
強め合う場所を結んだ曲線を腹線, 弱め合う場所を結んだ曲線を節線という.
山(実線円)と山(実線円), および谷(破線円)と谷(破線円)の交点(●)をとって結ぶと, 腹線が現れる.
山(実線円)と谷(破線円)の交点(○)をとって結ぶと節線が現れる.
数学的には, 腹線は強め合う条件 S1P-S2P=mλ (m=0, 1, …)を満たす点の軌跡である.
このとき, 整数mを腹線・節線の次数 じすうといい, m=0の腹線を0次の腹線という.
例えば, 図の点 Pはm=1の腹線上にあり, 実際に距離の差はΔℓ=3λ-2λ=λとなっている.
節線は弱め合う条件 S1Q-S2Q=(m+1/2)λ (m=0, 1, …)を満たす点の軌跡である.
例えば, 図の点 Qはm=1の節線上にあり, 実際に距離の差はΔℓ=3λ-3/2λ=3/2λとなっている.
一般に, 2つの定点(焦点 しょうてん)からの距離の差が一定となる点の軌跡は双曲線となる(数学 C:2次曲線).
ただし, 2つの定点からの距離の差が0となる点の軌跡は, 2定点を結ぶ線分の垂直二等分線となる.
2つの波源を結ぶ線分S1S2上では, 逆向きに進む2つの同じ波が重なり合うため, 定常波が生じる.
定常波の波長は元の進行波と同じλであり, 腹と腹, 節と節の間隔はいずれもλ/2となるのであった.
2つの波源が同位相で振動している場合, 線分S1S2の中点は必ず0次(m=0)の腹線となる.
そこからλ/4ごとに節線と腹線が交互に現れるため, S1S2=2λ の場合, 腹線3本と節線4本が現れる.
腹線と節線の本数(mがとりうる整数の範囲)を数学的に求めることもできる.
実は, 干渉条件は三角形S1S2Pの成立条件 S1P-S2PS1S2 (幾何的要件)を満たす必要がある.
ここで, 波源上は定常波の腹・節にはなるが曲線はできないので, 腹線・節線の本数としては数えない.
よって, 三角形S1S2Pの成立条件に等号を含めていない.
三角形の成立条件を満たす0以上の整数mの個数から, 実際に現れる腹線・節線の本数が決まる.
このとき, 腹m=0の直線を除けば, 1つの次数mに左右2本の曲線が対応することに注意する.
上図の場合, 腹線はmλ<2λ よりm=0, 1であるから, 合計3本存在する.
節線は(m+1/2)λ<2λよりm=0, 1であるから, 合計4本存在する.
水面上の2点S1(0, 5/2), S2(0, -5/2)から, 波長2.0mの同位相の波が速さ5.0m/sで
伝わっているとする. 有効数字は考慮しなくてもよい.
(1) 点A(12, 5/2)と点B(21/4, 5/2)は強め合うか, 弱め合うか.
(2) 腹線と節線は何本生じるか.
また, 線分S1S2上の定常波の腹の位置をy座標で答えよ.
(3) (2)において, S1とS2の振動が逆位相である場合, 答えはどのように変わるか.
(4) 線分S1A上には, 強め合う点がいくつ存在するか(端点を除く).
(5) ある時刻に点Aで生じていた干渉状態(2つの波の位相の組合せ)が移動し,
1.0s後に点Aと同じ位相の組合せで干渉する点の座標を答えよ.
(1) 点A
S2A-S1A=12^2+5^2-12=13-12=1.0=λ/2より, 弱め合う.
点B
S2B-S1B=(21/4)^2+5^2-21/4
=29/4-21/4=2.0=λより, 強め合う.
(2) 右図より 腹線5本, 節線4本.
腹の位置 y=-2.0, -1.0, 0, 1.0, 2.0 [m
幾何的要件と強め合う条件よりmλS1S2=5
m<5/2より m=0, 1, 2 ∴ 腹線は5本.
幾何的要件と弱め合う条件より (m+1/2)λS1S2=5
m+1/2<5/2より m=0, 1 ∴ 節線は4本.
経路差 Δ L=(2.5-y)-y-(-2.5)=-2y=2y
強め合う条件は 2y=mλ=2m (m=0, 1, 2)
∴ 腹の位置 y=-2.0, -1.0, 0, 1.0, 2.0 [m
波源を結ぶ線分上にできる定常波の腹と節の数を図を描いて数えるのが簡潔かつ確実である.
まず, 経路差が0となる波源の中央を考える. ここは, 同位相ならば必ず腹, 逆位相ならば必ず節となる.
後はλ/4ごとに節と腹を交互に取っていくと, 自然と腹と節の数がわかる.
別解は,三角形S1S2Pの成立条件S1P-S2PS1S2=5を満たす次数mの個数を数える方法である.
強め合う条件S1P-S2P=mλ, 弱め合う条件S1P-S2P=(m+1/2)λより, mの個数が求まる.
垂直二等分線に対応する場合を除き, 1つのmに対して2本の双曲線が対応することに注意して答える.
腹の位置も, 強め合う条件S1P-S2P=mλを用いて数学的に求めることができる.
腹の位置を P(0, y)とすると, 2y=2mよりy=±mとなる.
m=0, 1, 2である.
逆位相の場合, 強め合う条件と弱め合う条件が逆転し, それに伴って腹と節の位置も逆転する. →(3)
(3) 右図より 腹線は4本, 節線は5本.
腹の位置 y=-1.5, -0.5, 0.5, 1.5 [m
幾何的要件と強め合う条件より(m+1/2)λS1S2=5
m+1/2<5/2より m=0, 1 ∴ 腹線は4本.
幾何的要件と弱め合う条件より mλS1S2=5
m<5/2より m=0, 1, 2 ∴ 節線は5本.
経路差 Δ L=(2.5-y)-y-(-2.5)=-2y=2y
強め合う条件は 2y=(m+1/2)λ=2m+1 (m=0, 1)
∴ 腹の位置 y=-1.5, -0.5, 0.5, 1.5 [m
(4) (1)より点Aはm=0の節線上にあり, (2)よりその上方にm=1, 2の腹線が存在する.
よって, 線分S1A上の強め合う点は2個である.
線分S1A上の点をC(x, 5/2) とする.
強め合う条件は S2C-S1C=x^2+5^2-x=mλ=2m
x=25-4m^2/4mとなり,を満たすのはm=1, 2より, 強め合う点は2個.
同位相の場合, 中央にm=0の腹線, その両側にm=0の節線, m=1の腹線, … と交互に並ぶ.
よって, 線分S1Aが何本の腹線・節線(双曲線)と交わるかを図形的に判断することができる.
別解は, 強め合う条件S1P-S2P=mλを用いて数学的に求める方法である.
x^2+25-x=mλ x^2+25=x+2m x^2+25=(x+2m)^2 x=25-4m^2/4m
この方法ならば, 線分S1A上の強め合う点の座標が(9/8, 5/2), (21/4, 5/2)であることも確認できる.
(5) 波の速さ5.0m/sより, red1.0s後には波面(位相)は5.0×1.0=5.0mだけ外側へ進む.
1.0s後に点Aと同じ位相の組合せになる点をX(x, y)とする.
S1X=S1A+5.0=12+5.0=17,S2X=S2A+5.0=13+5.0=18
よって, 各波面の式は x^2+(y-5/2)^2=17^2, x^2+(y+5/2)^2=18^2
∴ 連立して X(x, y)=(122, 7/2)
平面上の2点から広がる円形波の干渉状態(位相の組合せ)が時間とともにどう移動するかが問われる.
時間の経過に伴い, 各波源を中心とする波面(同位相面)の半径は, 進行距離の分だけ大きくなる.
上図は, 点 Aにおいて, ちょうどS1からの波が山, S2からの波が谷となっている瞬間の図である.
わかりやすさのために山と谷の組合せを示しているが, 本問においては山か谷かは重要ではない.
点A通過時の位相の組合せが何であれ, その位相は1.0s後に半径を5.0m増やした円上に到達する.
結局, 点Aと同じ位相の組合せは, 1.0s後, 半径を5.0m増やした2つの円の交点Xに現れる.
多くの問題では, いくつかの点の候補が与えられ, その中から選ぶだけでよい.
しかし, 本問のように座標まで問われた場合には, 円の方程式を用いて数学的に求めることになる.
時間が経過しても, 2つの波源からの進行距離は同じだけ増えるため, 経路差は変化しない.
よって, 点 Aで成り立っていた経路差1/2λの弱め合いの条件は, 時間が経過しても常に保たれる.
ゆえに, 節線上にある点Aでの位相の組合せは, 時間とともに, 節線上を外側へ移動していく.

