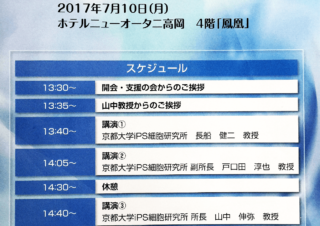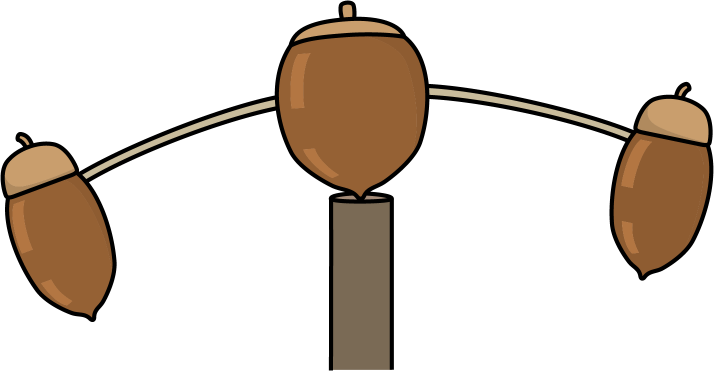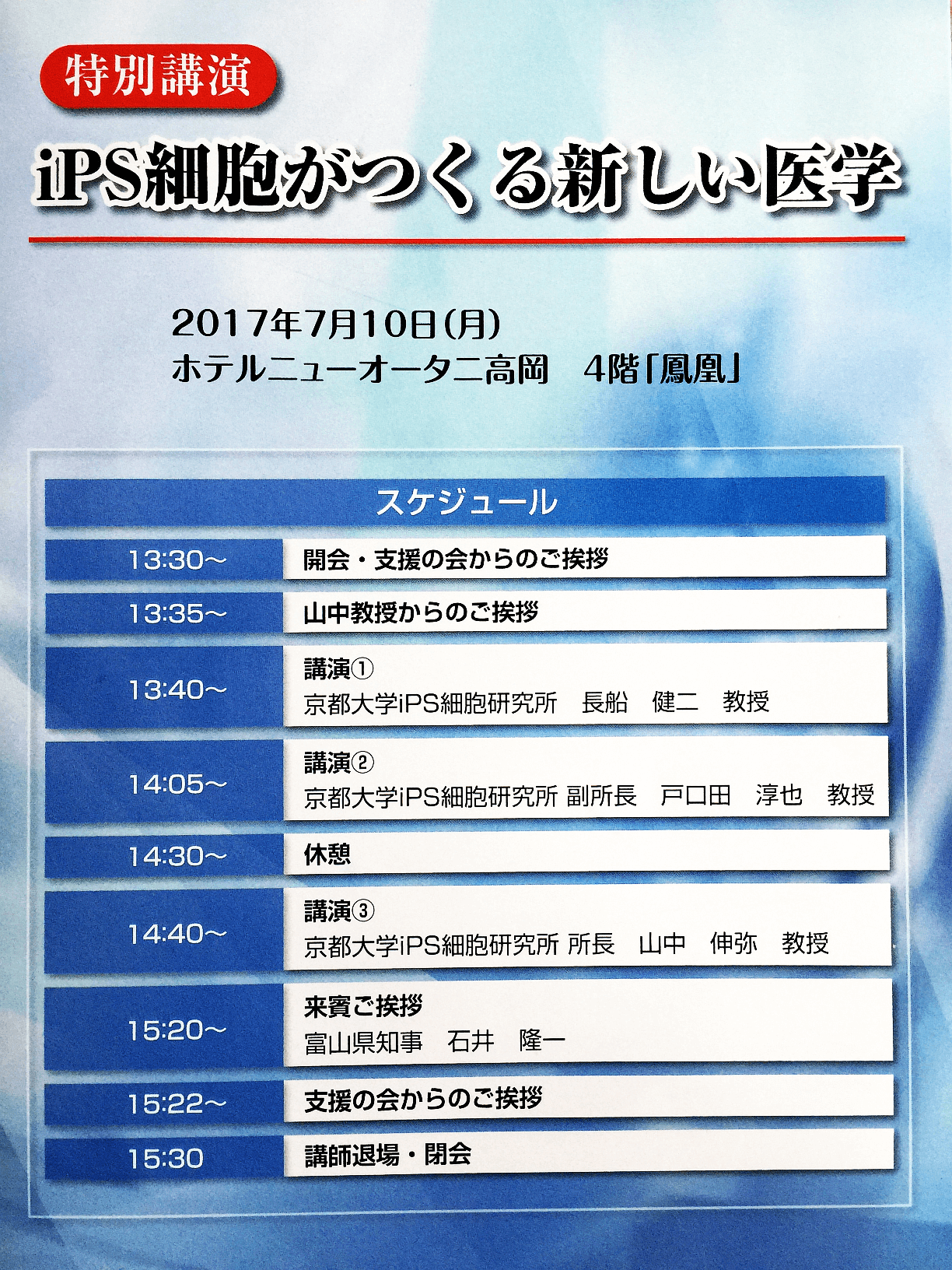芦田愛菜様が絶賛!
2016年、有名子役の芦田愛菜はあまりテレビで見かけなくなっていた。「人気が落ちた?」「もう大人になって使い道がなくなった?」などという意見も聞かれたが、実際は難関中学受験に備え、仕事をセーブして塾にも通いながら1日12時間以上勉強していたのだった。そして2017年、彼女は偏差値70以上の慶応中等部に合格し、進学した。他にも、女子校御三家の女子学院や滑り止めの数校に全て合格していたが、芸能活動が認められている慶応中等部を選んだようである。芸能活動で自分で稼いだお金で塾に行っていたのかな?(笑)
受験終了後、彼女をテレビで見る機会が増えてきた。彼女は読書が趣味で、12歳にしてすでに1000冊以上読破したという。その彼女がある番組で「人生で最も魂が震えた一冊」として絶賛した書籍こそ、『山中伸弥先生に、人生とiPS細胞について聞いてみた』(講談社)である。
念のために言っておくが、山中伸弥氏はiPS細胞を世界で初めて作成して2012年にノーベル生理学・医学賞を受賞した医学者である。
彼女は9歳のときにこの書籍を読み、山中教授が「人間万事塞翁が馬」という中国故事を座右の銘としていることに感銘を受けたという。この故事は、「人生の幸せや不幸は予測できないので一喜一憂すべきではない」ことを主張している。幸せだと思っていたら突然不幸が訪れたり、不幸だと思っていたら突然幸せが訪れるといったことが人生では起こりうるのである。
書籍の中で、山中教授の人生がまさにこの故事を体現してきたようなものだったことが記されており、彼女も「この先辛いことがあっても一喜一憂せずにチャンスと考えよう」と思ったそうである。
幼い頃から細胞に興味を持っていた彼女が、この書籍と出会い、将来の目標として医者や薬学者を公言するようになったのも自然な流れなのかもしれない。
本書を中高生に推奨する理由
ということで管理人も読んでみた結果、予想を遙かに超えた感銘を受けた。ただし、彼女とは違う部分で。
人生何が幸か不幸かわからないというのは、大人ならば誰しもが少なからず経験してきたはずである。よって、今更このことに感銘を受けたりはしない。
管理人がこの書籍を中高生が読むべき一冊だと考えるのは、「研究とは何か」「研究者はどうあるべきか」「研究者に必要な能力」が非常にわかりやすく具体的に記されているからである。これは研究者になる前にある程度知っておくべきことで、なってから知ったのでは手遅れになる可能性がある。それゆえ以前から話しておきたいと思っていたのだが、まともに研究をしたことがない中高生に説得力を持つ説明をするのはあまりに難しい。その点、すでにノーベル賞受賞という結果を出した山中教授の言葉や経験はそれだけで説得力を持つ。
「自分は研究者になるつもりはないから関係ない」と思う中高生もいるかもしれない。しかし、何も大学の実験室で行う科学研究だけが研究ではない。アスリートになるにしてもトレーニング法や勝つための戦略を研究する必要があるし、普通の会社員であっても自社の売り上げを伸ばすための研究をする必要があるだろう。将来どんな道を歩むにしても研究は避けられないのである。そのため、大学受験を目指す学生にとってだけではなく、人生の指南書としても極めて優れている書籍である。
また、ノーベル賞受賞までの過程は非常にドラマチックであり、単純な読み物としても面白い。決して順風満帆だったわけではなく、多くの紆余曲折があった。長い間成果が出せず、誰にも理解されず、「自分はいったい何をしているんだろう」と人知れず涙を流したこともあった。うつに近い状態にまでなってしまったこともあった。
山中教授が実際に何を考え、何を経験し、何を学び、何を教え、最終的にノーベル賞受賞に至ったのか、そして今後の展望。フィクション(創作)では絶対に味わえないノンフィクションならではの感動である。
分量も多すぎず少なすぎず適度で、専門知識も必要なく、1、2時間程度で読み終えることができる。読書感想文の題材としても強く推奨できる。
以下では、この書籍の中で特に個人的に着目した部分と、それについての個人的な意見や関連事項を話しておくことにする。あらかじめ断っておくが、以下で話すのは書籍の内容のごく一部に過ぎない。他にも多くの興味深い記述があるので、実際に書籍を読んで確認してもらいたい。
難病の前では臨床医は無力
山中は、大阪教育大学付属高校卒業後神戸大学医学部に進学し、その後整形外科医になる道を選んだ。しかし、すぐに挫折を味わうことになる。20分で終わるはずの手術に2時間かかってしまうほど手術が下手だったのである。研修期間の2年間、指導医の先生に「ジャマナカ」と言われ続けたという。
研修期間中、山中は自分の能力と共に臨床医(直接患者を診る医者)の限界も感じ始めていた。リウマチ、骨肉腫(骨のガン)、脊髄損傷など、どんな名医でも治せない難病患者に接する機会が多くなったからである。
iPS細胞による治療法の開発が期待されている難病の中で、山中教授が特に象徴的なものとして取り上げているのが、ALS(筋萎縮性側索硬化症)である。
10万人に1~2人くらいの難病であり、管理人がこの病気を知ったのは2014年である。当時、世界中でアイスバケツチャレンジが話題になっていた。これは、指名された人が頭から氷水をかぶって動画を投稿し、また次の人を指名するといったものであり、ALSの認知度向上や研究資金集めの目的があった。有名人が行ったものはテレビでも報道され、その中には山中教授が氷水をかぶっている動画もあった。
管理人は、アイスバケツチャレンジがはやっていた頃はALSという難病があるらしいというくらいの認識しか持っていなかったが、2017年に日本テレビの「ザ!世界仰天ニュース」で取り上げられたことによって初めてALSという病気の現実を知ることとなった。
凄まじい現実に愕然とするしかない。
筋肉の萎縮により、全身が徐々に動かせなくなっていく。今日動いた部分が明日動かなくなる。体が動かせなくなっていく一方で、意識や全身の五感だけはずっと正常なままという生き地獄である。約5年で自発呼吸ができなくなり、人工呼吸器を付けるか死かの二択を迫られる。患者本人はもちろん、家族にとっても想像を絶する環境に追い込まれる。その結果、日本では約7割ものALS患者が死を選ぶという。人工呼吸器によって生きながらえたとしても、最終的にTLS(完全な閉じ込め状態)と呼ばれる段階に到達する患者が一定数存在する。体のすべての部分が完全に動かなくなり、意思表示や外部とのコミュニケーションが完全にできなくなる最も恐ろしい状態である。繰り返しになるが、五感や意識は正常なままである。
番組で取り上げられた女性は、夫と2人の子供と共に生きることを選んだ。彼女は現在、パソコン画面の文字を目で追うことで家族とコミュニケーションをとっているという。最後の砦となった今はまだ動く目で・・・。
医学の道を志したものがこの現実を目の前で見たとき、「自分が何とかしてあげたいが臨床医にはどうしようもない。根本的な治療法のための基礎研究が必要だ。」と強く思うのも当然であろう。
繰り返したハッタリ
書籍の中で、山中教授は人生の分岐点において何度かハッタリをかましたことを述べている。
1回目は、1989年大阪市立大学大学院の薬理学を受験したときである。臨床医から基礎医学への転向を考えて受験した山中だったが、薬理学の知識がなく面接でしどろもどろになってしまった。仕方なく、最後にやけくそで「薬理学はわかりませんが研究したいんです!通してください!」と叫んだ。後に面接官だった先生に「あのとき叫ばなければ落としていた」と言われる。能力ではなくやる気で合格したのである。なお、現在採用する立場となった山中は、成績によらずやる気のある人を採用したいという。
2回目は留学先を探したときである。山中は大学院卒業後、遺伝子改変マウスの作成技術を習得したかったが、当時日本で扱っている研究室がなかったので留学しかなかった。何のコネもなく、ポスドクの求人広告に30~40通ほど手当たり次第に応募したものの、良い返事が帰ってくることはなかった。そこで、先輩の「正直に書いても採用されないから分子生物学の実験もできますと書け」というアドバイスに従って応募したところ、アメリカの研究室から返事が届き、電話で30分ほど会話して契約が成立した。電話では、「Do you work hard?」と聞かれて「Yes, I do.」と答えたという。ハッタリをかましたので喜んでばかりもいられず、分子生物学の実験手法を3ヶ月で学び、1993年サンフランシスコに渡った。
3回目は帰国後に奈良先端科学技術大学院大学の求人に応募して面接を受け、「ノックアウトマウス(遺伝子組み換えマウス)を作れますか?」と聞かれたときである。アメリカで複数人でしか作成したことがなかった山中は、正直に「一人ではできません。」と答えると採用されないと考え、「すぐにできます。」とここでもハッタリをかました。1999年、奈良先端科学技術大学院大学の助教授として採用され、初めて自分の研究室を持つことになった。
別にハッタリを推奨するわけではないし、美談にするつもりもない。所詮は成功者の結果論にすぎない。
サッカー日本代表の本田圭佑もそうだが、ハッタリやビッグマウスにより、あえて自分をそうせざるを得ない環境に追い込むことによって本領発揮できるタイプの人がいる。ハッタリをかましたとしても、有言実行すればもはやハッタリではなくなるというわけである。
研究者としての資質
大阪市立大学大学院生として初めて行った実験が、山中が研究者人生を歩む上で大きな影響を与えた。山中が行ったのは、指導教官が立てた仮説が正しいかどうかの検証であった。
ワクワクして行った初めての実験で、仮説に反して予想もできなかった結果が得られた。このとき、山中は自分が研究者に向いていると感じた。
というのも、多くの人は仮説が外れるとがっかりする。次のような人は自然科学の研究者には向いていないだろう。
「何だよ・・・。期待通りの結果が得られないじゃねーかよ。やってられるか!!!」
一方、山中は予想外の結果に心底興奮したという。
「ええーっ!面白い!何でこうなるの!!!自然ってすごい!!!」
この原因を探るのが山中の大学院での研究テーマとなり、博士号の取得につながった。
大学院生時代に山中は3つのことを学んだ。
- 科学は予想通りにならないからこそ面白い。
- 想外のことが起こるので、実際に患者に試す前に十分な検証が必要である。
- 先生のいうことは当てにならない。先入観を持つべきではない。
このような研究者としての資質は、学校の成績とはあまり関係がないという。もし学校の成績が思わしくないという理由だけで研究者を諦めようとしている学生がいるならば、それは間違いである。例えば、センター数学で高得点をとれるか否かは計算力によるところが大きい。しかし、分野や内容にもよるだろうが、科学研究において個人の計算力が常に必要とされるわけではない。計算などパソコンに任せておけばよいからである。もちろん基礎学力は必要なので、学校の勉強が全く役に立たないわけでも決してない。
最も大切なのは、自分が興味を持ったことを純粋な気持ちで徹底的に追求しようとする姿勢である。山中は毎日早朝から深夜まで泊まり込みで実験に没頭し、アメリカ留学中は人の3倍働いた。このとき、医学部時代に試験勉強とラグビー部の活動を両立していた経験が生き、1つの実験の待ち時間に他の実験をするなどうまくスケジュール調整できたという。
自然科学の研究者には向いていない人がいたとしても、別にそれは悪いことではない。「人間万事塞翁が馬」である。人それぞれに価値観・性格・特性などの違いがあり、自分に合った居場所で自分の役割を果たせばよい。研究者、政治家、公務員、サラリーマン、アスリート、芸能人、医者、弁護士、専業主婦、様々なタイプの人が様々な役割を様々な場所で果たして初めて1つの社会が作られる。全員が同じ特性を持っていて同じ役割を果たそうとするとそれこそ社会が成り立たなくなる。社会は多様性を必要とするのである。
実際、山中教授とは逆に、研究者を目指して大学に進学したが、自分が研究者には向いていないことに気づき大学を去った人間もいる。この人物をAとする。Aは、大学での研究の何たるかを全く理解しておらず、学校の試験や理科の実験や受験と同様のものと思っていた。つまり、答えや結果があらかじめわかっている問題に対して教官が期待した解答をするのが研究だと思い込んでいたのである。そんな状態で研究室に所属した結果、何をやっていいかもわからず、邪魔者扱いされる日々が続く。「やる気がないならもう来なくていい」と言われたこともあった。Aはその当時、自分が何故怒られているのかが理解できなかった。大学を卒業する頃には研究者になることなど考えもしなくなっていた。その後、Aは回り回ってようやくインターネット上に自分に合った場所を見つけ、そこでくだらないことをやって満足しているという。
iPS細胞の作成からノーベル賞受賞まで
我々は皆、1つの受精卵から始まる。それが細胞分裂を繰り返しながら、皮膚になったり筋肉になったりして1つの個体ができあがっていく。この受精卵を元にして1981年に作られたのが万能細胞とも呼ばれるES細胞である。様々な細胞に分化していく受精卵を元にしているので、ES細胞が万能性(様々な細胞に分化する能力)をもつのは当然と言えば当然である。ES細胞を必要な細胞に分化させ、患者に移植するという再生医療への応用が期待される。しかし問題もある。受精卵を元にするということは、受精卵を壊すということである。そのままいけば新たな命になるはずの細胞の破壊には倫理的な問題が伴う。
山中は、受精卵ではなく体細胞(たとえば皮膚の細胞)から万能細胞を作成できないかと考えた。つまり、我々の皮膚などの細胞を万能細胞に変えようというのである。これなら倫理的な問題は生じないが、簡単ではないことは明らかだった。普通、一旦分化した細胞が他の細胞に変わることはない。皮膚細胞が突然脳細胞に変わったりなどしたら大変である。一方で、理論的に可能であることは他の研究者によって既に示されていた。山中は、「理論的に可能ならば必ずいつかは実現できる」という強い信念をもっていた。
一旦分化した細胞を分化する前の受精卵のような状態に戻すという「細胞の初期化」への長い道のりが始まった。山中は、当初「定年までに何とか実現できれば」と考えていた。
山中は、アメリカ留学中にプレゼン力の重要さも学んでいた。研究者は5割が研究、5割がプレゼン力だという。とかく日本人は良い研究なら放っておいても評価されるなどと考えがちだが、十分にアピールして人や金を集めなければ研究ができないのである。
2003年、山中は科学技術振興機構のプロジェクトに応募した。山中のプレゼンがプロジェクトの総括者である大阪大学総長の目にとまり、2億5000万円の研究費を獲得することができた。1000万円以上する機械で1回何十万円もかかる実験が可能になり、初期化に必要な遺伝子を24個にまで絞り込んだ。
24個の中から本当に必要な遺伝子を特定するために1個ずつ皮膚細胞に送り込んでみたが、初期化されなかった。山中が途方に暮れていたとき、研究室の初期メンバーでもある高橋和利が驚くべき提案をした。「24個全部入れてみます。」普通、送った1個の遺伝子が細胞に取り込まれる確率は数千個に1個くらいの割合であり、生物学の研究者は24個同時など絶対に無理と考えてやってみようとはしない。工学部出身で生物学の素養がなかった高橋だからこその柔軟な発想だった。
実際に24個入れてみると、万能細胞に近いものができてしまった。初期化に必要な遺伝子が24個の中にあることがわかったが、ではそのうち2個か3個か4個か・・・。24個から何個かを選ぶ組み合わせは1500万通り以上もあり、それだけの実験をする時間も金もない。ここで高橋がまたしても驚くべき提案をする。「1個ずつ除いていけばいいのでは。」本当に初期化に必要な遺伝子ならば、1個除いただけで初期化できなくなる。1年間の実験の末、ついに細胞の初期化に必要な4つの遺伝子が特定された。これは「山中4因子」とも呼ばれる。
わずか4つの遺伝子だけで細胞を初期化する方法はあまりにも簡単すぎた。情報が漏れてしまうと簡単に成果を横取りされてしまう。結局、論文発表まで成果を知っていたのは山中を含めて4人だけであった。
山中は以前に、自分が発見して名付けた遺伝子の名前が使われず、外国の研究者が命名した名前が一般的になって悔しい思いをしていた。一般的にも覚えやすく親しみやすい名前にすることを考え、当時流行していたiPodにあやかって「iPS細胞(人工多能性幹細胞)」と名付けた。
2006年に山中がマウスiPS細胞作成を発表したことで、ヒトiPS細胞作成の開発競争が始まった。山中らは、マウスiPS細胞作成の論文を発表する前から実験を開始し、ヒトでも可能であることはわかっていた。
2007年、アメリカ出張中に他の研究室がヒトiPS作成に成功しているという噂を聞いて山中は焦った。すでに論文作成に必要な実験データは集まっており、帰りの飛行機内で慌てて論文を書いてすぐに投稿した。時差のために何度も徹夜で編集者とやりとりし、11月に発表されることになった。この1週間程前、世界で初めてヒトES細胞を作成したアメリカのトムソン教授から「競争に負けたのは残念だが、相手がシンヤでよかった」というメールが届いたという。ヒトiPS作成に成功していたのはトムソン教授だったのである。当初山中の論文が1日前に発表される予定だったが、異例の対応によって同日に掲載された。
もはや山中のノーベル賞受賞は確定的なものとなっていた。他のライバル研究者にとっても、同じ研究分野からノーベル賞受賞者が出れば、自分の研究が世間にも注目されるきっかけとなり、人や金が集めやすくなる。ノーベル賞選考委員会には、世界中の研究者から「早く山中にノーベル賞をやってくれ」との催促があったという。
その結果、2012年、2006年の論文発表からわずか6年という近年では異例の早さで山中教授はノーベル賞を受賞した。カエルの細胞の初期化によって世界で初めて細胞の初期化が可能であることを示し、山中教授(50)と共同受賞したイギリスのジョン・ガードン博士(79)は、山中教授が誕生した1962年の論文での受賞である。最先端の研究であるほど評価に時間がかかるため、ノーベル賞受賞者の多くが高齢者である。死者には与えられない決まりなので、最も大きな受賞条件は長寿であることとされるくらいである。医学応用が実現されていない段階であっても、iPS細胞の作成は圧倒的な成果であり、その可能性を認めざるを得なかったのである。
山中教授とiPS細胞技術の未来
言うまでもなく、山中教授の最終目標はノーベル賞の受賞ではない。受賞後、「これからは研究者に戻り、もう二度とノーベル賞のメダルを見ることはないだろう」と述べている。
また、本書のインタビューの最後で、「重圧を感じないか」と問われた山中教授は次のように答えている。
東日本大震災があり、日本の経済も決していいとはいえない状況の中、CiRAは毎年数十億円もの血税を使わせて頂いているのですから、成果を上げて社会に還元する使命がぼくらにはあります。しかし、一年や二年で、iPS細胞の技術を患者さんに直接使ってもらえるようになるわけではありません。その段階に至るまでには、10年から20年かかると見ています。ぼくの使命は、マラソンと同じように、患者さんにこの技術を届けるまで、バテずに走りつづけることだと思っています。
(略)
iPS細胞という技術と出会ってしまったので、(自分に重圧がかかるのは)当然のことだと思います。それこそ、「なんで自分がこんな目に遭わなあかんのか」っていいたくなるのは、ALSなどの難病を患う方たちのほうだと思います。ぼくはマラソンも走れるし、お酒も飲ませてもらっているわけだから、彼らの苦しみとぼくの苦しみはまったく次元が違います。でも、ぼくらががんばったら、彼らの苦しみを少しでも減らせる可能性がある。
(略)
ぼくは医師であるということにいまでも強い誇りを持っています。臨床医としてはほとんど役に立たなかったけれど、医師になったからには、最後は人の役に立って死にたいと思っています。父(享年58)にもう一度会う前に、是非、iPS細胞の医学応用を実現させたいのです。
2006年に山中教授がマウスiPSの論文を発表してからすでに10年以上が経過し、iPS細胞の医学応用が現実のものとなってきている。
2014年には、失明原因が欧米で1位、日本で4位とされる目の難病「加齢黄斑変性」を対象に、理化学研究所がiPS細胞による臨床手術を行い成功した。iPS細胞技術がヒトに応用された世界初の事例である。
また、日本には10万人以上の脊髄損傷患者がおり、さらに事故などで毎年新しく5000人が患者となる。一度損傷してしまうと回復することはなく、体を動かせないまま一生を終えることになる。しかし、iPS細胞によって脊髄を再生することが可能になってきた。すでにマウスはもちろん、猿での実験にも成功している。動けなかった猿が走り回れるようになっているのである。2018年にはついにヒトでの臨床試験が開始されようとしている。
密かにハゲに対してもiPS細胞技術が期待されている。山中教授が「自分も期待したいが難病が優先」と言ったとか言ってないとか。iPS細胞技術が髪の領域に突入する!!!
こちらの記事もどうぞ。
iPS細胞の最新情報はこちらへどうぞ。